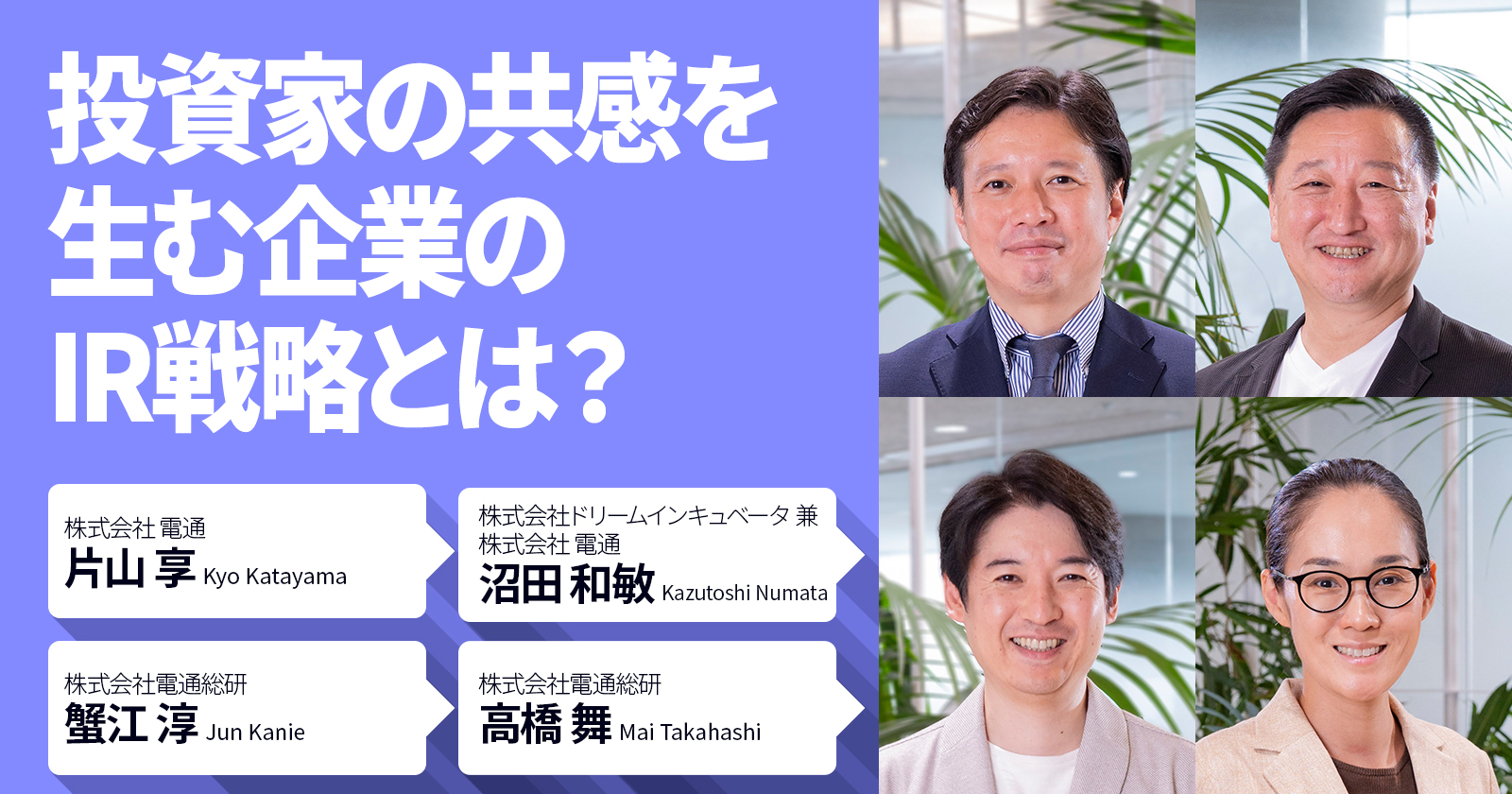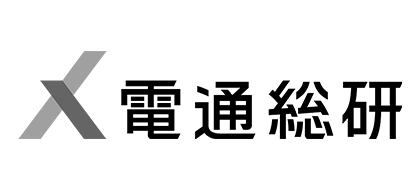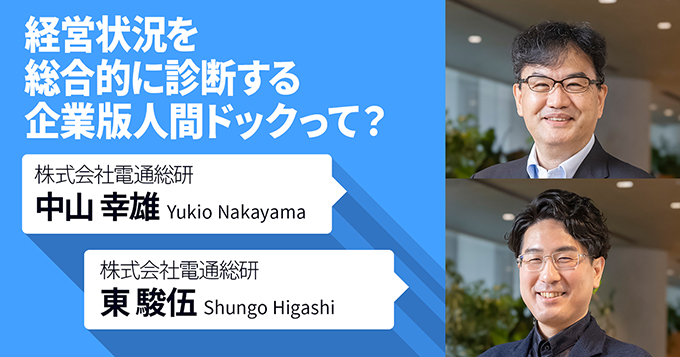サステナビリティ経営や人的資本開示の潮流を背景に、IRコミュニケーションに注力する企業が増えており、今やIR活動は、企業価値向上につながる重要なファクターです。にもかかわらず、ステークホルダーの共感を得る非財務価値を十分に打ち出せていない企業も少なくありません。
こうした課題に対応すべく、国内電通グループ(dentsu Japan )では、企業のIR支援に加えて、財務・非財務の両面からコンサルティングを行い、中長期的な企業価値向上を支援するプログラム「IR For Growth 」の提供を開始しました。本プロジェクトには、株式会社 電通 トランスフォーメーション・プロデュース局 部長の片山享氏、新たな事業や産業の創造・企業の成長支援を行う株式会社ドリームインキュベータ 執行役員兼 電通 トランスフォーメーション・プロデュース局の沼田和敏氏、財務と非財務の価値向上をテーマにコンサルティングメニューを開発してきた株式会社電通総研 コンサルティング本部の蟹江淳氏が参画。人的資本経営案件を数多く手がけている電通総研 コンサルティング本部の高橋舞氏を加え、投資家目線での企業価値向上の在り方について聞きました。
なぜ?今、企業の持続的な価値向上がIR視点で見直される理由 Q.なぜ今、企業の持続的な価値向上の観点からIRが再評価されているのでしょうか。
片山: 2023年3月、東京証券取引所は上場企業に対して、資本コストや株価を意識した経営への改善を要請しました。その後、投資家視点を踏まえた経営に関する施策や留意点も公表され、要請内容が具体的に示されるようになりました。それに加えて、TOPIX(東証株価指数)の採用ルールが変更され、上場基準は年々厳しくなっています。上場維持のボーダーライン上にいる企業はもちろん、各社にとって企業価値の底上げが喫緊の課題とされ、経営陣の関心も非常に高くなっています。
株式会社 電通 片山 享氏 Q.現在、上場企業の約半数が、株価が1株当たりの純資産を下回る状態、いわゆる「PBR(Price Book-value Ratio/株価純資産倍率)1.0倍の壁」にぶつかっています。その理由や、日本企業が抱える課題についてお聞かせください。
片山: 少子高齢化が進む日本では、人口減少に伴い市場がシュリンクしていきます。こうした中、事業体の筋肉質化や業態の転換、新規事業の創出が強く求められています。2025年7月にはエンタメ産業主要9社が、自動車産業9社の時価総額を上回るなど、セクターによって投資家からの期待値に差が見られます。歴史ある企業ほど、事業ドメインを大きく変革していくことが必要であり、今まさに多くの企業がチャレンジしているのではないかと思います。
Q.PBRを上げるためには、どのようなアプローチが考えられるのでしょうか。
片山: “PBR=ROE(自己資本利益率)×PER(株価収益率)”です。PERには企業の将来性に対する市場の期待値が反映されていると言われており、投資家の心を動かすIRコミュニケーションがPER向上に結び付きます。持続的な成長への期待値を高めるには、人的資本を充実させ、パーパスに向かって全社一丸となって駆動することが重要だと考えています。
沼田: ROEを高めるために、新しい収益の柱を作りたい。そういった考えもあり、新規事業への参入を検討される企業さまは結構いらっしゃいます。実際、われわれコンサルタントのもとにも、そうした相談をいただくことはあるのですが、新規事業は単に着手するだけでは意味がありません。当たり前のことですが、事業として継続し、収益を生み出して、はじめてROEに貢献します。分かってはいるものの、十分な収益につながらないままさまざまな事情で終了してしまい、残念な結果に終わることもあります。
株式会社ドリームインキュベータ 兼 株式会社 電通 沼田 和敏氏 投資家の共感を生む、財務・非財務価値を統合した成長ストーリー Q.皆さんは、多くの企業の経営層の方々と日々向き合っています。どのような課題が上がっていますか?
片山: 既存事業の収益は悪くないものの、株価やPBRがなかなか伸びないという声をよく聞きます。また、非財務領域や人的資本経営に力を入れながらも、投資家にその価値が十分に伝わっていないというご相談もあります。多くの企業では中期経営計画を公表しますが、事業部ごとの中期戦略や、コーポレート基盤側の人的資本戦略などがバラバラに策定され、一貫性のあるストーリーになっていないケースが数多く見られるんです。このように事業活動とHR、IRが分断される中、各部署を束ねて中期ビジョンや成長ストーリーに横串を通す(一貫性を担保する)役割を期待して電通にお声がけいただくことが増えています。
蟹江: 企業内でも、企業価値の受け止め方が変わってきているように感じます。従来は株主第一主義的で、いかにして事業を成長させ利益を上げるか、その点をどう発信していくかという財務価値が重視されていました。ですが、昨今はマルチステークホルダー主義がうたわれ、社会的価値の提供が求められるようになりました。それに伴い企業の目標設定も変わり、非財務価値向上への意識が徐々に各部署にも浸透しつつあるように思います。
株式会社電通総研 蟹江 淳氏 沼田: 後はアクティビスト(もの言う株主)の声への対応、というのも話題に上がりますね。アクティビストから突き付けられた厳しい指摘に対し、経営者はどう応えていくべきか常に考えさせられていると思います。財務価値を高めるために既存事業の改革に取り組み、新規事業にも着手したものの、株価は思うように上がらず、どうしたものか、というお声を聴いたりもします。いろいろなパターンがあるので一概には言えませんが、よくあるのが一番収益インパクトのある事業への思い切ったリソースの振り向けなどができておらず、もったいないなと感じることがあります。
高橋: 私は企業の人事役員・人事部長とお話をする機会が多いのですが、視座の高い方は、従業員向けのHRコミュニケーション、投資家向けのIRコミュニケーション、外部に向けたPRコミュニケーションを垣根なく考えています。就活サイトでも行きたい企業の統合報告書を見るようにと就活生に勧めていますし、従業員を主なターゲットにしたヒューマンキャピタルレポートを発行する企業もあります。HR、IR、PRの垣根をなくすことが、企業価値向上の一手になるのではないかと思います。
株式会社電通総研 高橋 舞氏 dentsu Japanが提供するワンストップ支援の強み Q.こうした中、電通グループでは戦略的IR支援プログラム「IR For Growth」を開発しました。その強みを教えてください。
蟹江: 「IR For Growth」は、財務・非財務の価値を統合し、一貫性を持って適切かつ効果的に伝えることで、企業価値の向上を目指す戦略的IR支援プログラムです。企業が成長ストーリーを描く上で、大切なのは非財務価値の魅力を明確に示すことです。「IR For Growth」には、非財務領域における取り組みの価値を、データに基づいた根拠とともに可視化し、電通グループの力で効果的に発信できるという総合的な強みがあります。
片山: 未来の提供価値を定めるところから最終的なリレーションシップまで、一貫して伴走できるところに電通グループのユニークネスがあります。まず、現在の企業価値から今後の可能性を可視化し、その企業が未来に提供し得る価値、つまり北極星を定める。そして、そこに向かっていくための事業・財務戦略を考え、それらを下支えする非財務戦略はどうあるべきか、そのためにどのようなアクションを起こすべきか、戦略性のある成長ストーリーの構築を行います。それを従業員の皆さんにも落とし込み、投資家に伝え、ブランディングにより新たな投資家や新規顧客を増やすところまで、電通グループ各社の強みを生かしながらワンストップで支援できる点が大きな特徴です。
TOPIX採用ルールの改定により、現在約2,100社ある採用銘柄は2028年7月までに約1,200社まで減少するとされています。企業価値の底上げが求められる中、「IR For Growth」はIR支援から、財務・日財務のコンサルティング、成長ストーリーの構築・浸透まで一気通貫で支援しています。自社の強みと課題を整理する機会にもなるため、気になる企業の方は一度相談してはいかがでしょうか。後編では、財務と非財務の価値を統合し、企業価値向上へとつなげた成功事例を紹介します。
国内電通グループ(dentsu Japan)各社では、さまざまなアセットと知見を用いて企業の価値向上支援を行っています。IR活動や人的資本経営など幅広く相談を受け付けておりますので、CONTACTからお問い合わせください。
https://transformation-showcase.com/articles/655/index.html
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。