「脱炭素」と「カーボンニュートラル」は、進む気候変動を食い止めるための重要なファクターといわれています。これらの認知率や生活者の意識の変化などを明らかにしたのが、電通グループ横断のチーム「サステナビリティ推進オフィス」および「電通 Team SDGs」が主体となって行った「カーボンニュートラルに関する生活者調査」です。2022年1月に実施された第6回調査の結果からどのような傾向が見えてきたのか、調査を担当した株式会社 電通の林祐氏に話を聞きました。
前編では、林氏は「カーボンニュートラルの必要性への理解を進めることが当面の課題である」と語りました。後編では、カーボンニュートラルへの理解を進めるためには何が重要なのか、「企業」と「生活者」2つの視点から詳しく聞いていきます。
「カーボンニュートラル」=「経済学」になり過ぎないことが重要
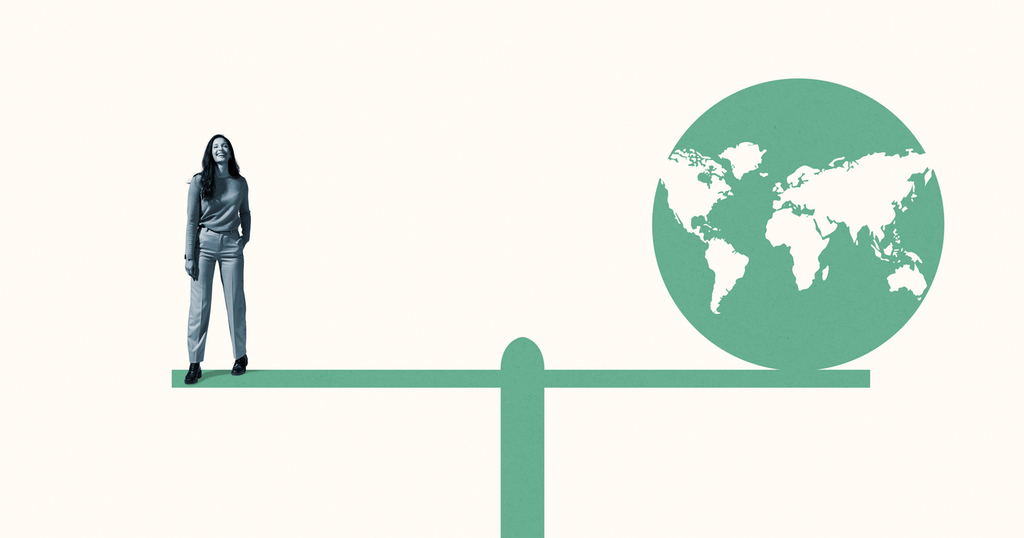
Q.既に調査を重ねること6回。林さんが感じている「今後の展望」について聞かせてください。
林:カーボンニュートラルという言葉が、脱炭素以上に市民権を得るようになった時に、そこにコミットする生活者は、どこにいるどのような人たちなのかを、しっかり見極めたいと思っています。この領域は、国や産業界が率先して取り組み、後から生活者が付いてくるという流れで進行しています。ただし、「付いてくる」と言っても、生活者にできることは今の時点ではそれほど多くなくて、「価格高騰を許容する」「カーボンニュートラルを進める企業に投資or就職する」「カーボンニュートラルが施された商品やサービスを選択する」程度の接点しかありません。ですから、人々がカーボンニュートラルにしっかりとコミットできるマインドかどうか、そして、それはどういうクラスターの人たちなのかを見極めることで、カーボンニュートラルを進めていく指針にしたいと思っています。
Q.林さんはこの調査に限らず、カーボンニュートラルというテーマでさまざまなお仕事をしていらっしゃいます。そんな林さんから見て、今後のカーボンニュートラルの理解浸透や定着について、あるいは将来像について、どのようなことを感じていますか?
林:少なくとも現時点では、カーボンニュートラルというテーマに対して、企業と生活者とで見えている世界や温度感に大きな差があるのではないかと思っています。
企業においては、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)を考慮したESG投資や、サステナビリティというものはとても大きなテーマになっているので、いろいろな取り組みをし始めている状況です。しかし、生活者からすると、BtoB領域やサプライチェーンにおける取り組みについてはほとんど見えていません。電気自動車のCMを見て「そうなんだな」と思う程度のきっかけしかないのではないでしょうか。そういう意味で、企業には、自分たちの取り組みを生活者にもっと分かりやすく発信していってほしいですし、ちょっと偉そうな言い方になってしまいますが、生活者も積極的に学ぶことも必要なのではないかと思います。
国は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を掲げ、成長が期待される14分野を提示しています。確かに、その分野の企業がイニシアティブを取って進めていくことが重要なのですが、最終的にカーボンニュートラルがドライブするためには、その他の全ての企業も推進役にならなければいけません。だからこそ企業の積極的な情報発信に期待したいのですが、この分野の情報発信が少し難しいのは、「『経済学』と『環境学』が並立してしまっている」ところにあるのではないかと。
どういうことかというと、企業による取り組みの発信は、主に「経済学」的な目線で語られることが多い。なぜなら、取り組みのゴールは「企業価値の向上」にどうつながるか、ということだからです。そのために、新しい技術を開発した、ビジネス構造を変えた、寄付をした、社会的インパクトに貢献したなどの情報を発信し、レピュテーションを高めたり、投資を集めたり、価格転嫁を許容してもらったりする。しかし生活者にとっては「地球の温度が上がって、今までの生活が脅かされている」という「環境学」の話として認識されてしまう可能性もあるのです。極端な話、ある企業がカーボンニュートラルに取り組んで企業価値がどうなろうと、生活者には関係ないことかもしれませんよね。生活者にとってもっと肌身に感じて重要なことは、明らかに昔と変わっている天候状況や、農作物や海洋資源が取れなくなってきた、という問題がどうなるのか。そして地球環境そのものが危ないということだったりします。この根本の食い違いがともすると忘れられがちで、企業からの発信が生活者に届きにくいのではないか、というのが私の仮説です。
そんな中でも情報発信が上手だな、と思う企業は、「こんな技術・商品をつくりました」ではなくて、「カーボンニュートラルを進めて、こんな街をつくりたいと思っています」という発信をしていますね。「これによってどういうライフスタイルになるのか」を想像させることができるので、生活者にとっても受け入れやすい発信になっていますし、「これからの社会をリードしてくれそう」という期待も獲得できているのではないでしょうか。
今こそ「受動的メディア」を上手に使うべき
Q.先ほど、「生活者も積極的に学ぶことも必要なのではないか」というお話がありました。とはいえ、学ぶこともなかなか難しいところもあると思うのですが。
林:私は、「カーボンニュートラルに関する生活者調査」だけではなくて、「SDGsに関する生活者調査」についても担当しています。最新の調査結果では、SDGsの認知率は86.0%となり、非常に高い割合となりました。ここ最近急に広まってきたという印象があるのですが、マスメディア、中でもテレビの影響が非常に大きいのではないかと感じています。これまではSDGsというと「報道」「教育」といった文脈でのみ登場していたものが、最近はバラエティ番組などでもSDGsをテーマにした内容が取り上げられるようになりました。カーボンニュートラルに関しても、SDGsのように、一般の方々が普通に生活している中で情報が出てくるようにならないと、普及はなかなか難しいのではないでしょうか。しかも、現代のインターネット中心の情報環境では、「自ら興味を持って調べないと届かない」情報が増えてきています。もし「受動的に情報に接する」テレビなどのマスメディアの地位が相対的に低下してしまったら、カーボンニュートラルという新しい概念が広がりにくいという影響も出てきてしまうかもしれません。
ちなみに、SDGsについては、若者の認知率や関心が高い傾向がありますが、これは教育の影響も大きいのではないかと思います。学校教育はもちろん、入試で出題されることも増えてきたので、自然と考えるチャンスが生まれる、ということも奏功しているのではないでしょうか。
Q.インターネット時代だからこそマスメディアの役割は重要、と言えるかもしれませんね。
林:今回の調査結果で私が個人的に強く感じたのは、まさにそこです。現代は、情報を「能動的に」取りに行かなければいけないことが多くなったため、実は新しいことを知るのが難しくなっている、という面もあるのではないか。だからこそ、テレビに限らずあえて「受動的に」情報を受け取れるメディアにも触れる必要があるのではと思いました。
例えば、「カーボンニュートラルに関する生活者調査」の第5回において、「COP26が開催され、地球温暖化対策について話し合われたこと」についての認知や内容理解を聞きました。COP26は、正式には「第26回気候変動枠組条約締約国会議」といい、国際連合の「気候変動枠組条約」に参加している国々によって行われる会議です。結果として、COP26の認知者は全体の53.4%と約半数。これを、「あれだけ報道があったのに、半分しか知らない」と捉えるか、「半分も知っている」と捉えるかは、考え方次第ですが、興味深いのは、この「COP26を知っている」と答えた人は、その内容についてもかなり知っている、ということが分かったのです。つまり、「知っている人は中身まできちんと知っている」し、「知らない人は本当に何も知らない」と、完全に二極化している。「情報」という領域においても世界が分断されてきている、と言えるかもしれません。最近の世界情勢についても、それなりに国際ニュースを見てきた人からすれば、文脈的に予想できた流れの1つだと考えられるし、そうでない人たちから見れば「突然世界が変わった」と感じる。私たちは、そんな時代を生きているのではないかと思います。
世界中が脱炭素の実現に向けて動き出している中、2030年の意欲的な目標に向けて、日本でも待ったなしの状況が訪れています。その中で、カーボンニュートラルの考え方は、浸透が進んでいるとはいえ、さらに社会全体に広げていく必要があります。
一方で、「情報の分断=世界の分断」という視点も重要です。社会課題が複雑化する中で、「自分の興味関心の有無に関わらず、社会的に重要な問題について把握できる」環境をいかに自分自身で整えていくかは、これからの時代を生きていく上で、とても重要なことかもしれません。












