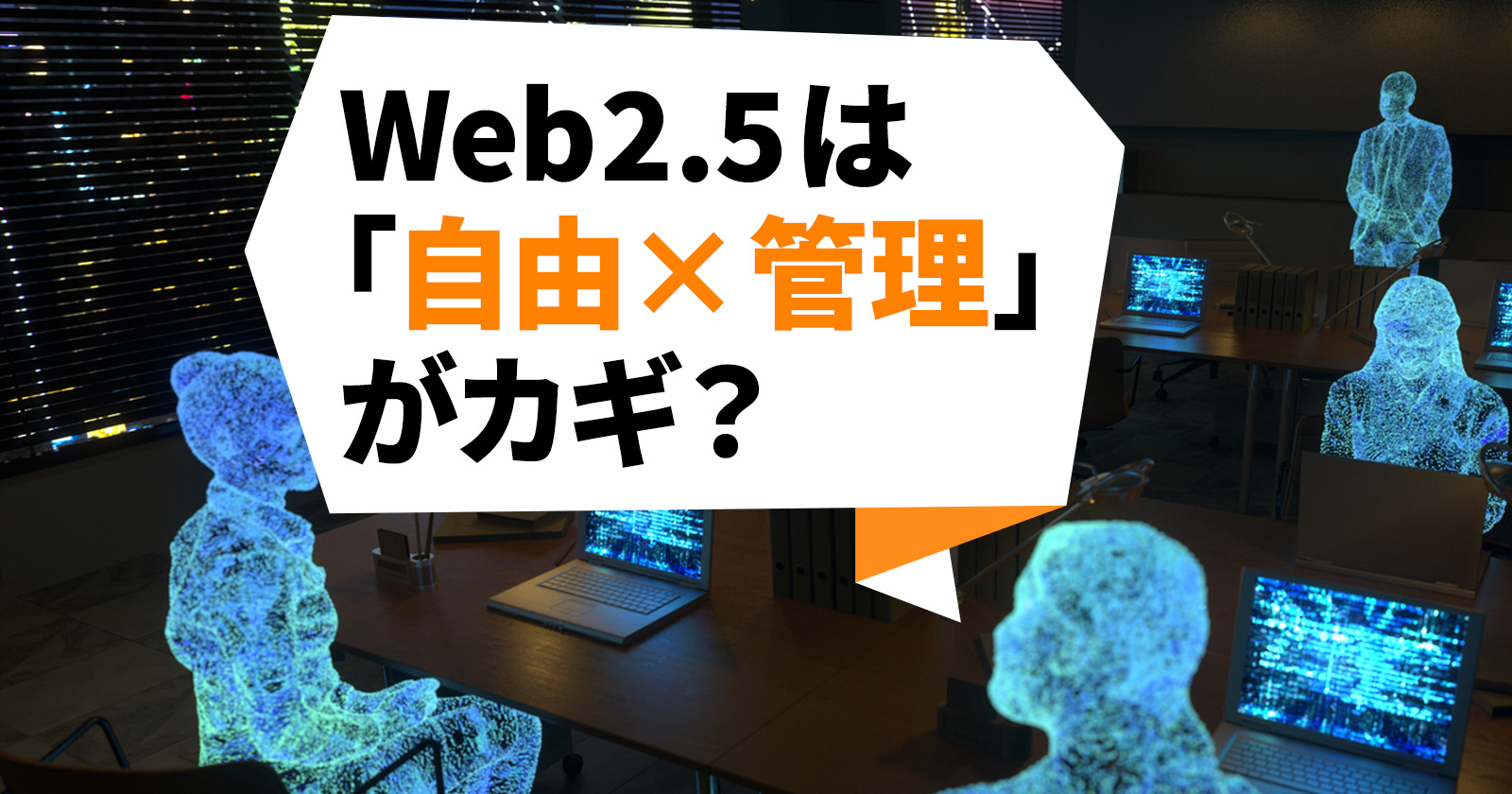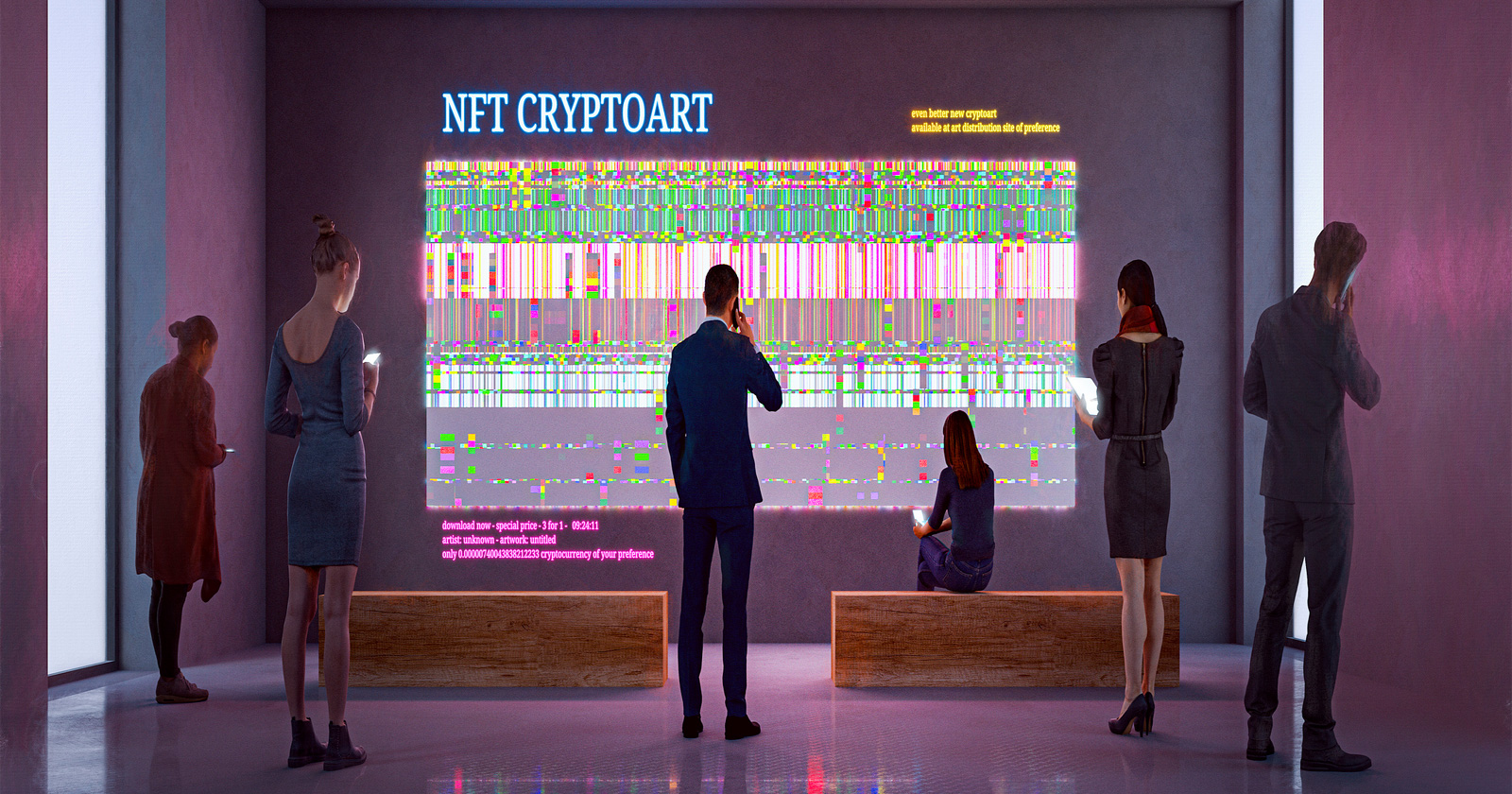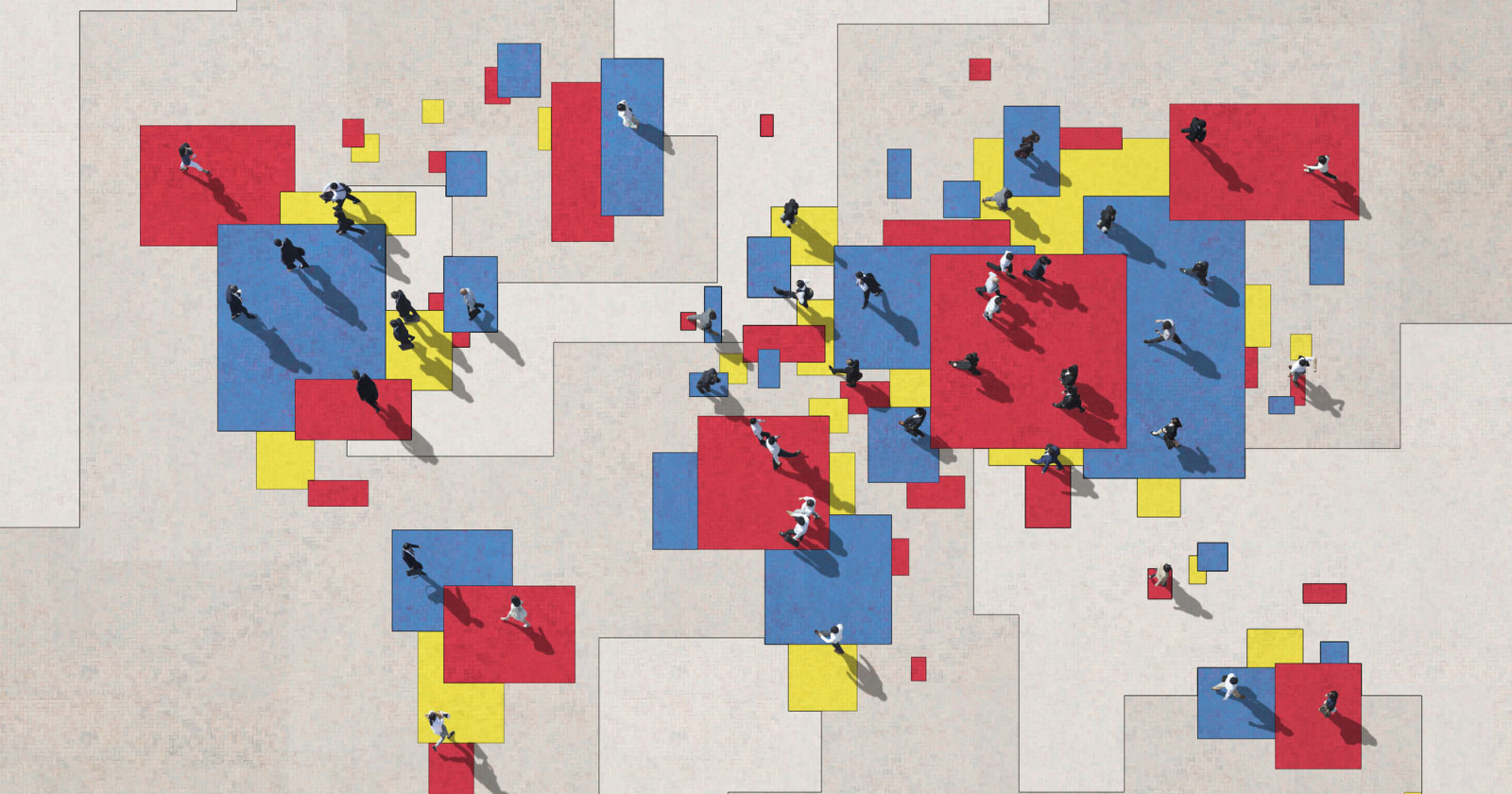近ごろ、ブロックチェーン、NFT、メタバースなど「Web3.0」について語られることが増えています。とはいえ、Web3.0が提示する非中央集権的な分散型管理を自社のビジネスにどうやって活用すればいいか、イメージするのが難しいという人も多いのではないでしょうか。今回は、「Web2.5型のメタバースはWeb3.0が成熟する礎となるか?」をテーマに、Webの今とこれからを考察。Web2.0とWeb3.0の“いいとこ取り”をしたWeb2.5型のメタバースから、ビジネスのヒントを探っていきます。
Web2.0とWeb3.0の間に位置する「Web2.5」とは?
2021年後半から、「Web3.0」というキーワードが広く語られるようになりました。しかし、「一時的な流行に過ぎない」「投機やマネーゲームに利用され、本質が置き去りになっている」など、懐疑的な見方をしている人が多いのも事実です。
そんな中、浮上したのが「Web2.5」で、ブロックチェーンを用いたマーケティングエージェンシーであるセロトニン社CEOのアマンダ・カサット氏が2022年3月に発言し、瞬く間に広まった考え方。Web2.5はその名の通り、Web2.0とWeb3.0の間を目指そうという動きを指します。ユーザーがWeb3.0を受け入れるには時間が掛かると予想されるため、Web2.5というクッションを挟んではどうかという提言です。
Web3.0についてはこちらの記事でも紹介していますが、ここであらためてWeb2.0とWeb3.0の違いについて確認しておきましょう。
Web2.0:中央集権型のインターネット
ユーザーがWebサイトを閲覧することしかできなかった1990年代から一転、2000年代以降になるとブログやSNSが登場し、インターネットの用途は「見る」から「参加する」へと移行しました。つまり、発信者と受信者の双方向のコミュニケーションが可能になったのです。その一方で、一部のグローバルプレーヤーの存在感が高まり、インターネット上において、ユーザー情報が集中することで、プライバシーやセキュリティの問題が注目されるようになりました。
Web3.0:自由分散型のインターネット
Web2.0の構造からさらに進化し、分散型管理を目指すのがWeb3.0です。ブロックチェーン技術により、ユーザー同士が直接つながり、経済圏を作り出していくムーブメントとされています。Web3.0では1人ひとりがデータやコンテンツを所有・管理し、ユーザー同士で情報やお金を直接やりとりすることが可能に。さらに、データの唯一性や希少性を証明する「価値証明」、過去のやりとりが全て記録される「透明性の保証」も、Web3.0の大きな特徴です。

このようなWeb2.0とWeb3.0の中間領域にあたるのが、Web2.5です。Web2.5は、Web3.0のように完全な分散管理ではなく管理組織はあるものの、Web2.0のように一部のプレーヤーにメリットが集中するのではない、いわば中間的な世界。
ステークホルダーがインターネットを管理するという「Web2.0的な組織形態」と、参加する全ての人や企業がクリエーターや生産者になり利益を分かち合うという「Web3.0的な思想」を両立。Web3.0が成熟していない状態だと、秩序を保てず利益の分配もうまく行われないことが危惧されますが、Web2.0的な管理者が秩序を守ることで参加者の自由や利益を守ることができる、と考えられています。
Web3.0に移行する前に、Web2.5を経由するのが現実的?
では、Web3.0に移行する前に、なぜWeb2.5というクッションを挟む必要があるのでしょうか。
先ほど述べたように、Web3.0はブロックチェーン技術が土台になっています。NFT(非代替性トークン)は、この技術を活用することでデータの唯一性や希少性を証明できる仕組み。そのため、価値の証明が求められるオークションハウスと相性が良いとされています。例えば、ある老舗オークション会社は、早期からNFTに着目。2021年4月に最初のNFT販売を始め、同年のNFTの売り上げは1億ドルを超えました。いち早くWeb3.0の本格化につなげた好例と言えるでしょう。
とはいえ、他のビジネスやサービスが一足飛びにWeb3.0に移行するには、ブロックチェーンの導入や活用というハードルがあります。技術的にもさまざまな投資が必要ですし、その運用についてもまだ安定しない面が多くあります。そこで、いきなりWeb3.0を目指すのではなく、あえてWeb2.5を経由する、という考え方が生まれたのです。現在、そんなWeb2.5型のインターネットを実現している代表例と言えるのが「メタバース」。現実とは一線を画す仮想空間で、参加者が対等に交流するメタバースは、Web2.0にWeb3.0の概念を取り入れたWeb2.5的な世界であると言えるのではないでしょうか。
メタバースをヒントに、Web2.5の道筋を考える
それでは、メタバースの最新動向を追うとともに、Web2.5についてさらに考察を深めていきましょう。
メタバースとは、大人数が同時に参加し、さまざまな体験を共有できるインターネット上の仮想空間のこと。こちらの記事でも紹介したように、以前からゲームの世界ではおなじみでしたが、2021年11月、当時のFacebook社が社名を「Meta(メタ)」に変更し、メタバース事業の推進を表明したことから大きな話題を呼びました。世界各国のテック企業も、メタバースのプラットフォーマーとなるべく激しい競争を繰り広げています。
そんな中、Web2.0の管理体系を維持しつつ、Web3.0の思想を運用に生かしたプラットフォームが登場。日本の企業が企画開発・運営するあるメタバースプラットフォームでは、中央集権型の運営体制でありながら、有料イベントの開催、有料ギフトアイテムやアバターの販売などを通じてユーザーが収益を得ることができます。
2000年代に登場した米企業が運営するあるバーチャル空間では、ユーザーが自由に空間を広げられる仕組みであったことからゲーム空間が過度に拡張し、人口密度が低下して過疎化が進んでしまいました。前述のメタバースプラットフォームはその事例を踏まえ、空間を拡張しすぎないよう中央で管理しつつ、ユーザーの利益共有を実現。参加者が一丸となって、独自の空間とカルチャーを育てています。

さて、メタバースにおけるWeb2.0とWeb3.0の考え方は、1つの組織が運営する「クローズドメタバース」と、複数のサービスが相互に行き交う「オープンメタバース」に重ね合わせることができます。1つずつ詳しく見ていきましょう。
クローズドメタバース
単一企業が、メタバースを運用している状態。こうしたクローズドな環境では、運用企業の影響力が大きいという点で、Web2.0に近い状態と言えるでしょう。2018年に公開されたスティーヴン・スピルバーグ監督の映画『レディ・プレイヤー1』では、巨大企業がVRゲームの運営権獲得をもくろみ、主人公たちを脅かす姿が描かれていました。仮想世界の一極支配は、現実世界にも大きな影響を及ぼすことが示唆されています。
オープンメタバース
複数のプラットフォームやサービスが、相互運用されている状態。マルチバース間での体験を均一に保ちながら、ユーザーが利益を共有できるオープンメタバースは、Web3.0に近い環境と言えます。1つの空間で問題が生じた際にも、分散型のオープンメタバースであれば、代替手段を多く確保できるのもメリットです。
インターネットによるデジタルコミュニケーションは、情報がバラバラに分散していたWeb1.0から中央集権的なWeb2.0になることで大きく発展しました。Web3.0は、ブロックチェーンなど新たな技術を生かし、インターネットを分散型で自由度の高い状態へ揺り戻そうという動きのようにも感じられます。
Web3.0の普及には、あと数年は掛かるとされています。自由であるが故に無秩序で制御が利かない状態が続けば、普及を待たずに廃れてしまう可能性もあるかもしれません。そうならないために、「プラットフォームを管理するプレーヤーがいるWeb2.0型」+「運用をユーザーに委ねるWeb3.0型」の“いいとこ取り”をしたWeb2.5を経由すれば、Web3.0への成熟がさらに進みそうです。企業も今後しばらくは続くと思われる過渡期に即して、Web3.0型の未来を見据えると同時に、現実路線においてWeb2.5型のビジネスの在り方を考えてみてはいかがでしょうか。
自由分散型のインターネット世界であるWeb3.0を目指すに当たって、まずはWeb2.0をベースにした「Web2.5」から始めることの妥当性について見てきました。また、Web2.5の最も分かりやすい例としてメタバースを挙げるとともに、Web2.0的な世界とクローズドメタバース、Web3.0的な世界とオープンメタバースを対比して、今後の組織やビジネスの可能性について考察してきました。Web3.0についてイメージをつかめず、なかなかアクションを取れずにいた方は、Web2.0とWeb3.0の“いいとこ取り”をしたWeb2.5の視点に立つことで、新たなビジネスのヒントが見えてくるかもしれません。
Web2.5型ビジネスを実現するにあたっての「初めの一歩」を知りたい。自社事業にWeb3.0のエッセンスを取り入れたい。そんな関心をお持ちの方は、未来志向のビジネスの創出を本気でご支援する電通ジャパンネットワークまで。まずはCONTACTよりお問い合わせください。