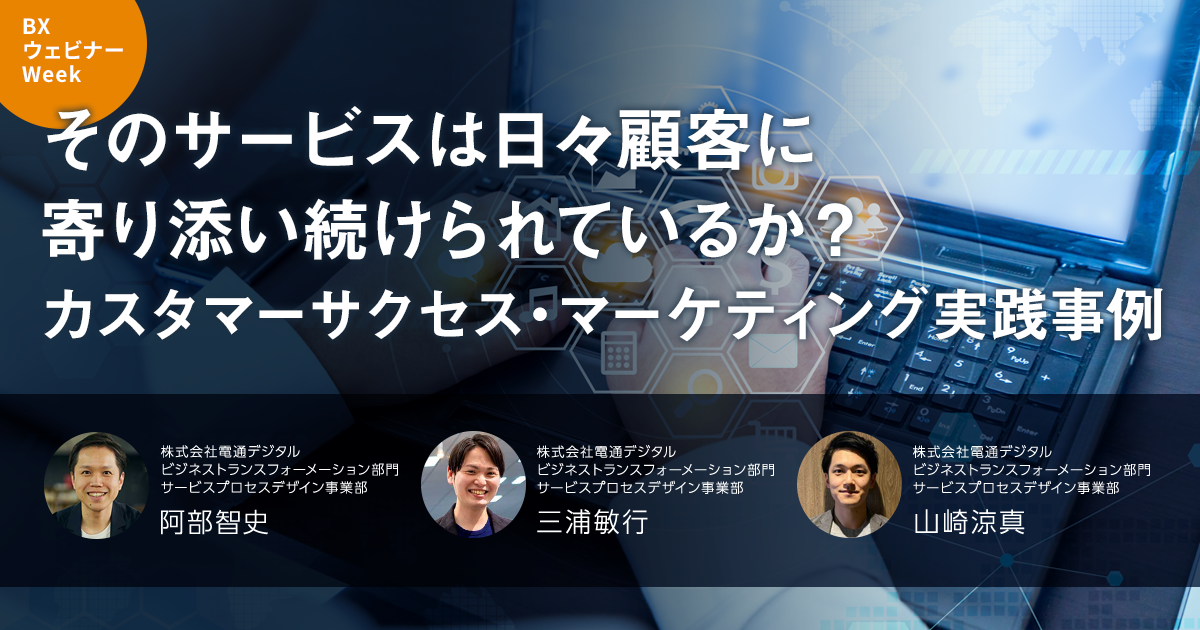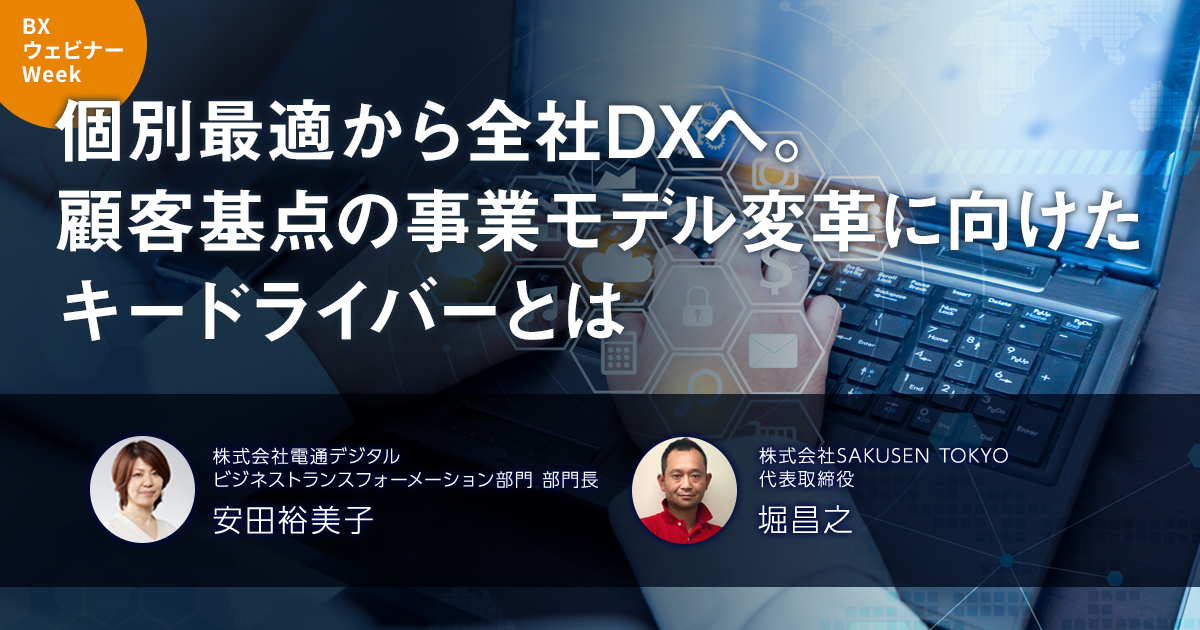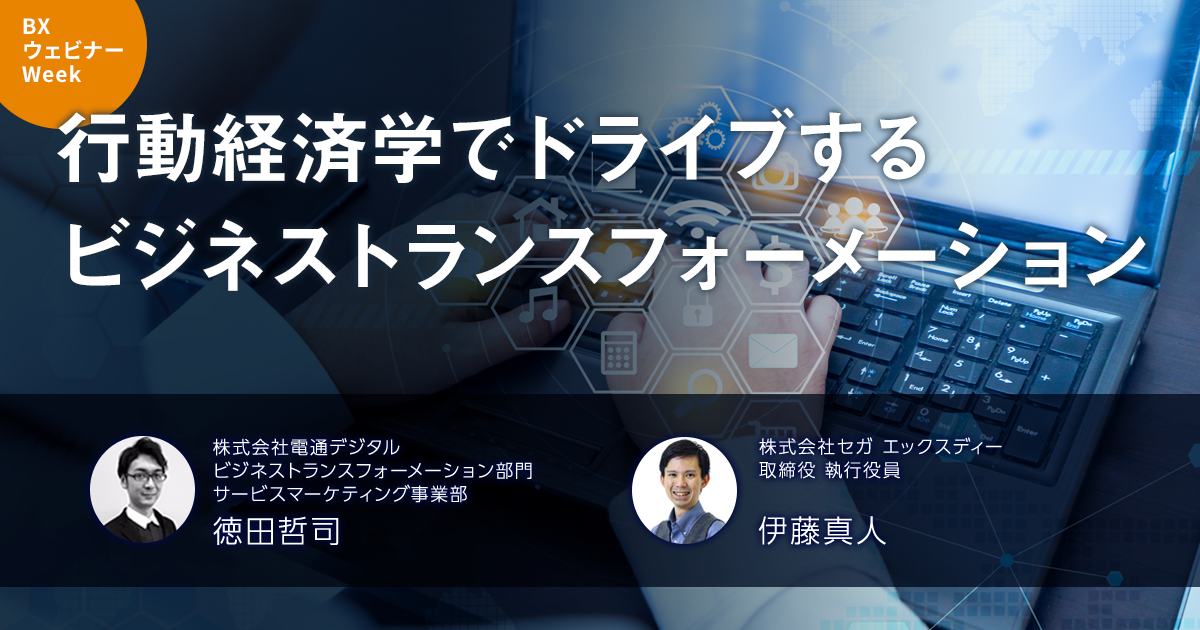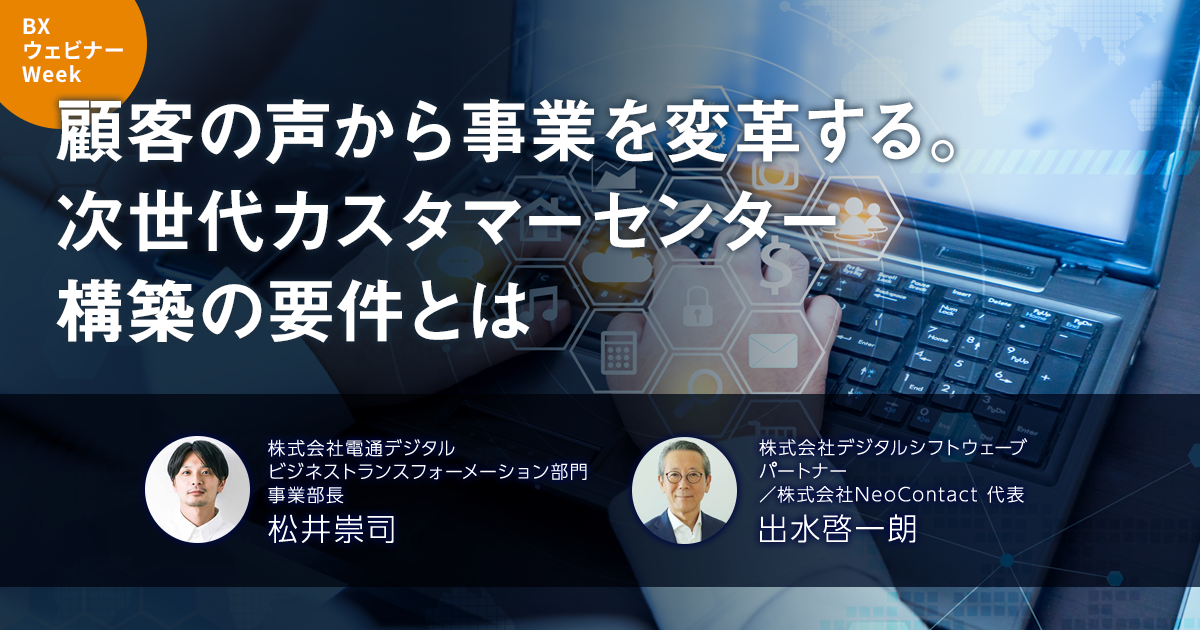2021年6月21~25日、株式会社電通デジタルは「今こそ求められる、“顧客中心のサービス企業”への変革 ビジネストランスフォーメーションに向けた実践知」と冠し、「BXウェビナーWEEK」を行いました。
6月22日の2回目は、電通デジタル ビジネストランスフォーメーション部門 サービスプロセスデザイン事業部 事業部長 清水彩子が登壇。直近の新規事業立ち上げ支援事例をベースに、データを経営資源として生かす「攻めの活用」において、1st Partyデータ(企業が自社の顧客やWebサイト訪問者に関して収集・保有しているデータ)の収益化に向けた、新規事業立ち上げのあるべき検討プロセスを紹介しました。
ビジネスに生かすデータの「守りの活用」と「攻めの活用」とは
ウェビナー冒頭、清水は「企業のデータ利活用の現状」について解説しました。2020年の総務省「デジタルデータの経済的価値の計測と活用の現状に関する調査研究」によると、企業活動において活用しているデータの種類を2015年と2020年で比較したところ、顧客データや経理データは変わらず多くの企業で活用されていました 。しかしPOSデータ、eコマースにおける販売記録データ、GPSデータ、交通量、気象データなどは、2015年に比べ2020年になり急激に活用する企業の割合が増えてきたのです。
出典:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/r02_05_houkoku.pdf
活用データが飛躍的に増え、企業内でもDX推進が叫ばれる今日、データを経済資源としてビジネスに生かす場合、大きく分けて2つの方向性があると清水は指摘します。
1つ目は「守りの活用」。主に効率化や事業改善に用いられ、既存のビジネスの売り上げを向上させる取り組み。2つ目は「攻めの活用」。事業開発などで用いられ、0から1を生み出すような新たなビジネスを創出する試み。
まず、方向性1「守りの活用」について見ていきましょう。
事業改善を行う場合、企業内のマイナス点を0にする試みのため、「効率化」「高度化」「最適化」が主たるテーマになります。「事業の可視化」とは、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールの導入などにより、実際に起きていることを可視化すること。そして今取り組むべきことを見やすくしたり、意思決定しやすくしたりするものです。
「発注最適化」では、例えば気象データなどを活用して受発注を最適化します。今までの受発注パターンをAIなどでデータ予測をし、発注システムにつなげていく。食品の廃棄ロスなどにも貢献できます。
「マーケティングの高度化」は顧客向けの施策です。例えば、身に覚えのないクーポンが届いて顧客体験を損なわないよう、過去のデータから読み解き、無駄なクーポンを削減するといった取り組みのことです。
上記のような施策で、業務改善をしたのが回転寿司店の「スシロー」です。全ての寿司皿にICタグを付けてデータを分析することで、どのような気象条件でどのネタが多く売れるかを事前に予測。さらに実際の店舗の意思決定を組み合わせ、タイムリーに求められているネタをお客さまに提供することで、廃棄量を4分の1まで抑えられたという好例です。
次は、方向性2「攻めの活用」です。
0から1を生み出す事業開発には、「データ販売」「新規サービス開発」「新サービス追加」 などの例があります。
「データ販売」は、銀行が自治体や法人に対して、統計データをWebサービスで外販するもの。匿名性を担保した上で、エリアにおける年収データをグラフで見せるなど、重要度の高いデータを見繕って掲載しています。
「新規サービス開発」の例として、ドラッグストアの広告事業があります。広告主から預かった課題に対し、自社のデータを活用し、ターゲットのアプローチから購買、結果の効果測定まで行います。
「新サービス追加」には、自動車販売のサブスクリプションサービスが挙げられます。既存のサービスにコネクテッドで走行データをフックにしたポイントプログラムを取り入れるなどして、事業全体のアップデートを図ったものです。
事業開発の具体事例は、住友生命の「Vitality」です。保険事業に紐づく商品で、健康で長生きする顧客のポジティブサイクルをつくるもの。参加企業を募り、顧客とのさまざまな接点で得たデータを取得し、パートナー企業同士のコンソーシアムが動き出している状況です。
データの利活用は、企業によって期待値や活用の成熟度が異なり、それが取り組みにも如実に影響します。どの領域からデータ利活用を行うかは、個々の企業の状態を見ながら課題に応えるサービスを検討する必要があるのです。
データ利活用に関する令和の時代にふさわしい広告事業
次に清水が触れたテーマは、「電通デジタルがご支援した事例」です。清水は多く寄せられる相談として下記を挙げました。
ご相談の内容が多岐に渡る原因は、データビジネスは多種多様なため、自社にとってどのような展開が望ましいのかの判断がつきづらいからと、清水は述べます。電通デジタルに寄せられる相談の多くは、広告事業に関する課題です。清水もデータ利活用の着手において広告は、データの整備、顧客インサイトのラーニングという点で見て一番着手しやすい領域と語ります。
また、早いうちに広告事業のデータ利活用に着手すべき背景には、複数のWebサイトを横断してCookieを付与することができる「3rd Party Cookie」が、まもなく使えなくなることが挙げられます。個人情報保護の規制強化や同意なき利用が禁止される「Cookie規制」の強化により、顧客に広告でアプローチできるのは、1st Partyデータ(顧客の同意を得た個人情報)を持つ企業に集約される流れになるからです。
そのため、1st Partyデータの活用ニーズは今後ますます高まるでしょう。購買、決済情報などの有用な1st Partyデータを持つ企業、またはメディアや店舗などで大規模な顧客接点を持つ企業は、広告ビジネスにおける有効な資産を保有しているという点で、アドバンテージを持つことになります。
それでは、電通デジタルがご支援した事例を紹介しましょう。前述でも少し触れた金融サービス会社の支援事例です。
法改正により、銀行が銀行業以外のサービスを行えるようになったことを受けて、現在金融業界のデータ活用は活況を呈しています。具体的には、「方向性② 事業開発 例えば...」の図で示したみずほ銀行のデータ外販のほか、2021年7月にスタートした三菱UFJ信託銀行の情報銀行「Dprime」や、京都銀行・伊予銀行・西日本シティ銀行などが参加する地域金融機関向けマーケティングサービス「共同MCIFセンター」 のデータベース活用があります。
電通デジタルが金融サービス会社の広告事業をご支援するにあたり、留意点が3つありました。
- UX(ユーザーエクスペリエンス)…広告提供形態の決定
- 競合優位性…USP(ユニークセリングプロポジション)の抽出
- 個人情報利用…法律の遵守
「1. UX(ユーザーエクスペリエンス)」は、顧客へのメッセージ、文脈を損なわないかが焦点になります。バナーは適切なところに掲出されているか、その上でコミュニケーションスタンプは必要かなど、フォーマットの決定をしていきます。この場合の具体例は、下記のようなものが挙げられます。
- 銀行のWebサイトで振り込みをする際に、広告がたくさん出たら邪魔にならないか
- 高級車を広告したい場合のターゲティングについて
例えば、「30代・年収1,000万円の男性」のような富裕層ターゲティングをした場合、「なんで振り込みをしたいのに広告なんか出てくるんだ」となりかねません。一方で、3年前から車のローンを組んでいる人をターゲティングして、「車検を通すか悩んでいたら?」といった広告を表示するのであれば、顧客にとっては「そういえば…」とピンと来て、気が利いた提案となるかもしれません。
次に「2.競合優位性」のポイントを解説します。銀行同士の場合、保有するデータは近しいものになります。そこで、自行が持つ資産で有益なものは何かを考え、自社が持つ独自の強みを抽出するのです。こちらの具体例は下記になります。
- 行内のユニークなデータをドッキングできないか、加工できないか
- 行内だけでなく、どの企業と組むともう少しおもしろいことができるか。データ連携のほかに、運用体制も含めた想定協業先を検討
「3.個人情報利用」は個人情報を利用するため、法の遵守が大事になってきます。2018年5月に施行されたGDPR(EU一般データ保護規則)、Googleの3rd Party Cookie廃止、リクルートの「リクナビ問題」などにより、ユーザーデータの活用に関して、マーケティングの見直しが求められています。電通デジタルは、積極的なデータ利活用と顧客プライバシー保護を同時に進めるために、プライバシーに配慮したデータ利活用のルール作成や、ルールを管理できるツールの導入も支援しています。支援の対応ステップは下記の通りです。
- 利用データと利用範囲に関する規定
- 1の結果を踏まえた正しいデータ活用プロセスの設計と、ガイドラインの作成
- 「顧客同意」を踏まえた令和時代の「顧客データマーケティング」の実現
4STEPで行った支援実例のプロセスを紹介
最後に、電通デジタルの「ご支援事例プロセス」です。約1年半をかけ、全4STEPを終えたクライアント企業の広告事業導入の実例になります。
まずSTEP1でアセットの棚卸しをします。自社媒体や保有データの分析をし、どのように利用できるのかを見極めつつ、STEP2の新規プロジェクトなどの事業化調査であるフィジビリティスタディのフェーズに移行。そこでPoC、ターゲティング企業へのヒアリングなどから広告として成り立つかを精査します。その後、STEP3となるプライバシーポリシーの対応を経て、最後にSTEP4の運用設計です。広告事業をスタートするにあたり、組織からどのような人材配置を行うかについてもアサインを行います。
では、STEP1から具体的なプロセスを見ていきましょう。
STEP1の自社媒体分析では、どのような会員にどのチャネルでアプローチができ、その会員はどのくらいいるのかを把握します。さらに自社チャネルでの広告出稿と、データ連携で外部プラットフォームに広告出稿した場合のメディアの価値概算などを行います。さらに保有データを棚卸しするにあたって、どれほどの顧客データがあるのか、データ加工によって顧客セグメントをどのくらい作れるのか、グループや外部データとのマッチングで、保有データがリッチ化できるか否かを検証するのです。
次は、STEP2のフィジビリティスタディです。
これは電通デジタルが活用仮説を立てた上で、自社媒体の広告ビジネスの観点からデータに対する魅力度を確認するものです。仮説に対する評価を社内でまとめるだけでなく、不足するデータがある場合、めぼしい業界の広告主の担当者にヒアリングします。仮説にはないけれども、うまくいきそうなヒントが得られた場合、ほかにはないアイデアや魅力的な視点を洗い出して、展開の一助としました。
STEP3のプライバシーポリシーについては、前章で詳説しました。その他は、弁護士事務所との連携で法的な確認を取りながら、導入フェーズに進めるようお手伝いをしたり、上の図にあるようにプライバシーマネジメントのサービスをTreasure Dataとの共同で開発したりもしています。
4つ目は業務設計です。今まで扱ったことのないデータ活用の広告領域に関して、まずは社内で必要なメンバーを定義します。運用を行うにあたって人材が不足する場合、電通デジタルからプランナー、オペレーターといった専門職が必要に応じて常駐するなど、体制作りの提案も行っています。
最後に清水は「ワンストップでの事業企画・開発・運用までの支援体制を整えていること」「さまざまな業界の支援実績に基づいた企業ニーズの理解と顧客ニーズの理解」と、広告事業立ち上げにおける電通デジタルの強みを2点挙げ、ウェビナーを締めました。
※2021年8月26日電通デジタルコーポレートサイト トピックスにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。
※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。