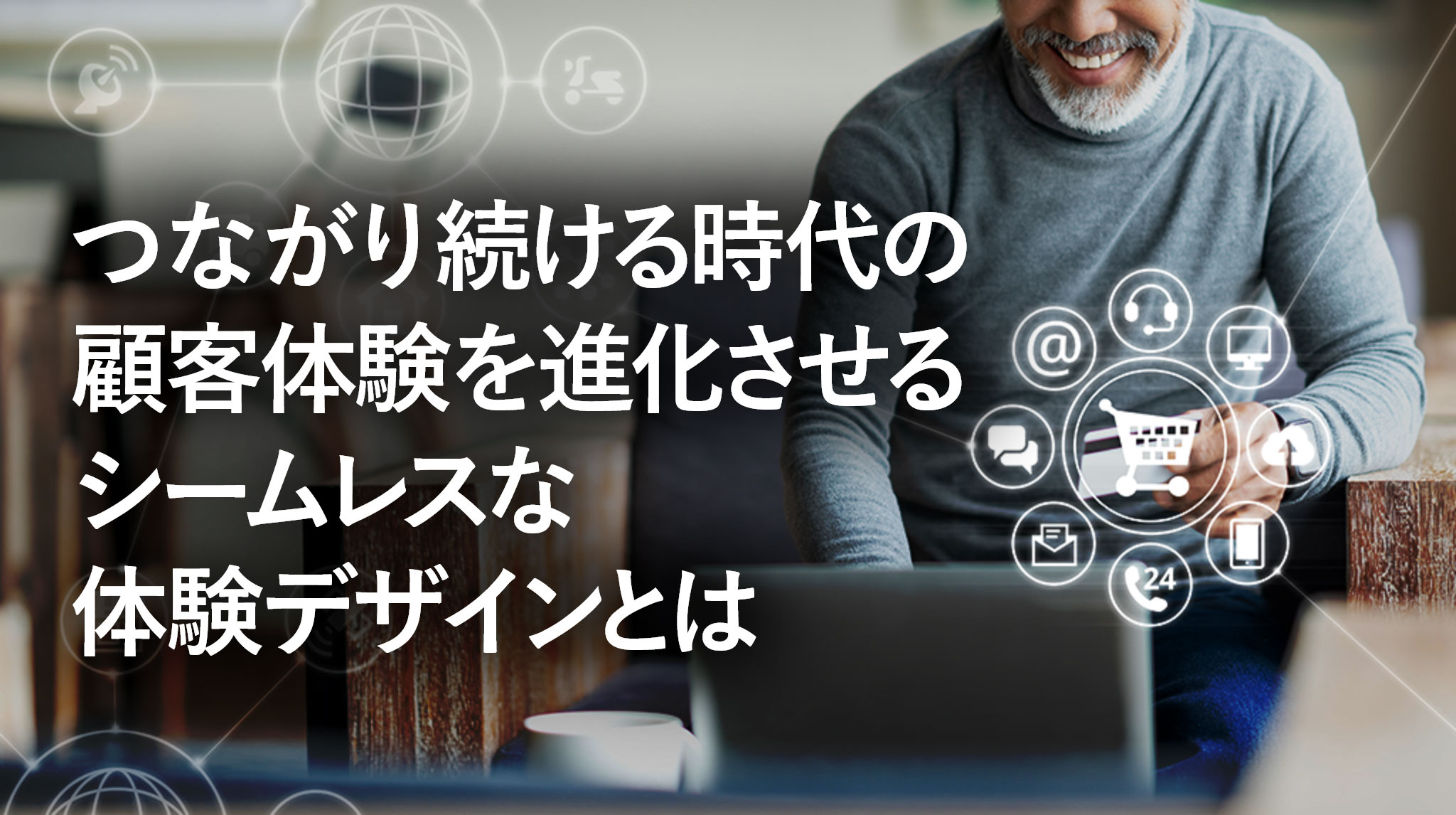国や地域の垣根を越えて、海外の商品やサービスをオンラインで購入する「越境EC」。ITインフラの普及やオンライン消費の広がりなどによって、近年高い注目を集めています。しかし、実際にこれまで海外との取引がなかった企業が、越境ECに参入するのは簡単ではありません。他国へ商品を売り込むにあたっては、ブランドイメージや情報の届け方を、相手国の文化や商慣習に沿った形で設計することが必要となります。戦略面においても「インターナショナルな感性を持つ」といったことだけでは片付けられない、複雑な課題に直面することは多々あります。また、海外のユーザーの信頼を獲得するためには決済や物流の安定性を確保することはもちろん、各国におけるECトレンドの深い理解も求められるでしょう。
この記事では、越境EC市場の現状や、日本企業の立ち位置について概観するとともに、日本発で展開するECの今後の可能性について考えます。また、GDPRをはじめ、越境ECに企業が参入する上で知っておくべきルールや、基本的なポイントについても押さえましょう。
拡大を続ける越境EC。今注目されている理由は?
越境ECは、国境を越えて行われる電子商取引のことで、ECサイトを通じて海外の顧客に商品を販売するビジネスモデルを指します。スマートフォンの普及やコロナ禍の影響などでECサイトの利用が増加している中、自国では手に入らない海外の魅力的な商品をオンラインで手軽に購入できる越境ECは、新たな消費活動の選択肢として世界的に広がりを見せつつあります。
越境ECにはさまざまなやり方がありますが、代表的なものとしては、以下のような方法が挙げられるでしょう。
1.自社で越境ECサイトを運用する方法
企業が独自に越境ECサイトを構築する方法で、国内向けに提供している自社のECサイトを多言語化するケースや、越境ECに特化したサービスを活用するケースも見られます。販売先の国・地域で、既に自社商品が浸透している場合には、現地で自社サイトを構築する方法も有効でしょう。
2.国内/海外のECモールに出店する方法
国内で越境ECに対応したモールに出店、あるいは、越境EC販売が認められている現地のECモールに出店する方法。モールへの出店は集客の面などで有利ですが、手数料や配送方法など、そのモールが設定するルールに従う必要があります。
3.代行販売サービスを活用する方法
メーカーと消費者の間に、運営代行会社が介入する方法です。現地の代行会社に商品を買い取ってもらい、そこから購入者に発送してもらうことで、自社からの発送や現地のユーザーとのやりとりなどの手間がかかりません。
4.保税区を利用して出店する方法
特に中国を相手にした越境ECで活用されているのが、保税区を利用した出店です。保税区とは、海外から輸入された物を、関税などを課税しない状態で保管できる区域のこと。この保税区の倉庫に商品を保管しておき、ECサイトで受注したら倉庫から顧客に配送することで、配送時間や配送料を抑えることができます。
越境ECが注目されている理由
日本を含め、世界的に越境ECに高い注目が集まっているのはなぜなのでしょうか?考えられる理由について見ていきましょう。
1.商圏を拡大できる
越境ECのメリットは何より、国内にとどまらず海外にまで商圏を広げられることです。今後、人口減少が進むことが危惧される日本では、人口の多いアジア圏や購買力の高い欧米など、海外の市場で顧客を獲得したいと考えている企業は多いでしょう。
2.低コストで始められる
海外に実店舗を出すより比較的低コストで挑戦できることも、越境ECに参入する企業が増えている理由の1つです。実店舗を出すには莫大な資金が必要となり、出店申請や現地スタッフの手配など準備にも多くの時間を要します。その点、越境ECはインターネット上の出店なので初期費用を抑えることができ、よりスピーディーに販路を海外市場へと広げることができるのです。
3.ITインフラの普及
世界中でITインフラが普及し、先進国だけでなく新興国でも、スマホなどのモバイル端末からのインターネット接続が一般的になりました。海外のECサイトへのアクセスが容易になり、自国の商品と比べながら欲しい商品を探して購入できるようになったことも、越境EC市場の広がりを大きく後押ししていると言えるでしょう。
4.コロナ禍による影響
コロナ禍によって渡航制限がかかり、インバウンド消費が落ち込んでいる中で、それに代わる方法として、越境ECに活路を見出している企業は少なくないでしょう。
越境EC市場は拡大中。アフターコロナではインバウンドとの相乗効果も期待

越境ECの市場規模は、年々拡大を続けています。経済産業省の「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」の報告書によると、2019年の世界の越境EC市場規模の推計は7,800億USドルで、2026年には4兆8,200億USドルに達すると推計されています。この間の年平均の成長率は約30%にも上ります。
国別で見ると、越境ECの購入先としては中国の存在感の大きさが際立っており、アメリカやイギリス、ドイツ、フランスなどにおける越境ECの購入先の第1位は中国です。
越境ECにおける日本の立ち位置
日本の越境ECの現状を見てみると、中国の越境ECでの購入先の第1位が日本、韓国での第3位も日本となっており、アジアでの影響力が強いことがわかります。前述の経済産業省の調査によると、2020年の中国の消費者による日本からの越境BtoC-ECの購入額は1兆9,499億円で、前年比で17.8%増という結果になっています。
一方で、アジア以外からの越境ECも拡大傾向にあります。アメリカの日本を対象とした越境BtoC-ECの購入額は9,727億円で、前年比7.7%増。また、ヨーロッパでは日本のアニメやゲームなどのコンテンツの人気が根強く、関連した商品が越境ECでも売れていると言われています。世界でどのような日本製品が売れているかを調査した、越境ECサポートサービスを提供するBEENOS株式会社による「BEENOS 越境EC 世界ヒットランキング2020」では、ヨーロッパの人気1位はおもちゃ・ゲーム、次いで音楽やファッション関連がランクイン。さらに、浮世絵や盆栽用具、武具など、日本の伝統文化に関連した商品も人気を集めています。日本から地理的な距離がある分、配送料や時間をかけてでも手に入れたい、こだわりの強い商品が売れている傾向にあるようです。
企業によっては「越境ECで具体的に何を売るか」が定まらない中、とにかく越境ECを始めるという手段だけが先走ってしまうこともあるかもしれませんが、こうしたトレンドのリサーチを参考に自社、あるいは顧客企業では何を売ることが有用であるかを考えることは非常に重要です。品質やデザイン性の高さを強みとした商品で時間をかけてファンを獲得したいのか、あるいはその時のトレンドに合わせて消費されていく商品をスピード重視で扱うのか。どちらが売れるか、という観点だけではなく、国というハードルを越えて「このブランドが求められるためには何が最適か」に重きをおいて計画を立て、必要なポイントを整理した上で課題を解決していくべきでしょう。
アフターコロナでも越境ECの好調は続く?
各国でEC市場が大きな広がりを見せている中、越境ECは今後ますます好調になっていくことが予想されます。さまざまなプラットフォームや代行サービスなどが登場したことで、参入障壁が下がり、大企業だけでなく、中小企業やD2Cブランドなどの越境ECへの参入もこの先、加速していくことが考えられます。
さらに、アフターコロナの時代を迎えれば、各国との人の往来が活発化し、インバウンド消費も再び増加に転じるでしょう。日本ではもともと、「日本で購入した商品を自国に帰ってからもまた購入したい」という訪日外国人が多く、越境ECはそうしたリピート購入の需要にも応えられる選択肢として、さらに利用者が増えることが期待されます。
また、言語や通貨の違いといった障壁を越えるテクノロジーも発展を続けています。システムの進化によって、ECサイトのセキュリティ面の強化や決済方法の簡素化など、利便性がさらに向上していけば、新たな顧客の開拓にもつながっていくでしょう。
加えて、海外の顧客と良好な関係を築き、ブランドの信頼性を高めていくことができれば、長く継続して商品を購入してくれるリピーターが増え、さらにビジネスを拡大していくこともできるかもしれません。例えば衣類や日用品であれば、商品の価値が海外の人々に浸透していくことで、リピーターが増加。それに伴い、海外の顧客に関するさまざまなデータも蓄積されます。そうなれば、国内ECと同じように、それらのデータを用いてオーダーメイドやカスタマイズ、パーソナライズといったサービスを展開し、より愛着を持ってもらうことができるようになるでしょう。その先には越境ECのサブスクリプションや定期購入などへの進展も考えられます。国内と海外でのサービス格差を小さくし、スケールメリットを大きくしていくことも期待できるかもしれません。
このように越境ECビジネスを拡大させていくためには、各国の商慣習やルールを知り、物流におけるトレーサビリティや地域事情などを理解することも必要です。越境ECに参入するにあたって、企業が知っておくべきポイントを次で紹介します。
越境ECに参入するなら、GDPRなどのルールの把握も重要

越境ECは、海外向けのビジネス戦略に加え、販売上の手続きや取引方法など、国ごとに異なる対応が求められる点に難しさがあります。最後に、越境ECに参入するにあたって、企業が知っておくべきポイントや注意点を確認しておきましょう。
海外市場のニーズをリサーチする
越境ECを立ち上げる際は、商品やサービスが海外市場でニーズがあるのかを見極めることが大切です。すでにその国で売れ筋となっている製品ジャンルに参入する方法もあれば、自社が扱う商品にニーズがある国をターゲットにする方法もあります。日本とは社会状況やユーザーの好みなども異なるので、現地の事情などを丁寧にリサーチした上で、国内以上に緻密な販売戦略を立てる必要があります。
現地において効果的なプロモーション方法を検討する
越境ECで利益を上げるためには、販促活動が成功のカギを握ります。例えば、現地で多くの人が利用しているSNSを活用する、中国であればKOL(Key Opinion Leader)と呼ばれる影響力のあるインフルエンサーを起用するなど、その国や地域にあわせて、効果的なプロモーション手法を取り入れると良いでしょう
物流のコストを抑え、利益が出る仕組みを構築する
越境ECは、海外への輸送コストが高額になる点がデメリットの1つです。販売価格に対して、顧客が負担する配送料が高額になれば、なかなか購入にはつながりません。顧客に直接配送するのか、現地に物流拠点を置くのかなど、利益を確保できる配送方法の検討は非常に重要になります。
現地の状況に合わせて決済方法を検討する
越境ECでネックとなりやすいのが、国ごとに異なる決済方法です。ユーザーに安心して利用してもらうためにも、現地でニーズの高い決済方法の導入は不可欠と言えます。自社で越境ECサイトを構築する場合は、ローカルな決済方法に対応しているプラットフォームを利用することも有効です。
当該国や地域の法律やルールに注意する
越境ECは、販売する国や地域の法律やルールに従って対応することが求められます。相手国の制度や必要な手続きをあらかじめ把握し、対応方針を固めましょう。
例えば、EUには、個人情報の保護について定めたGDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)というルールがあります。これは、越境ECを含め、EU圏内でグローバルビジネスを展開する上で知っておくべき法律です。GDPRでは、企業がEUを含む欧州経済領域(EEA)域内で取得した氏名やメールアドレス、クレジットカード番号などの個人情報を適正に取り扱うことを求めており、それらの情報を取得する際には、その目的や取り扱いについて明らかにすることなどを定めています。ECサイトなどを通じて、ヨーロッパに居住するユーザーとやりとりをする場合にも、このルールが適用される可能性があります。違反があった場合には罰則が科せられるため、ヨーロッパを含め、海外に向けたビジネスを展開する場合は、GDPRを遵守した対応環境の整備が必要です。
海外の巨大なマーケットへと販路を広げられる越境ECは、将来性のある魅力的なビジネスです。特に、日本製品は世界からの信頼が厚く、海外には潜在的なニーズもまだ数多く眠っているでしょう。アフターコロナを見据えたグローバル戦略の1つとして、日本企業が参入を検討する価値は大いにあると言えそうです。