多くの企業は、自社の商品やサービスの売り上げを上げるために、いかにして需要を喚起するかというテーマに取り組んでいます。そしてそのために、マーケティングコストを投下して販促につなげているでしょう。しかし、もし「需要が上がるタイミング」を事前につかむことができたらどうでしょうか。それが分かっていれば、「どこにマーケティングコストを投下したらいいか」を的確に把握することができるため、マーケティング効率は一気に高まります。
テクノロジーの進化とともにマーケティングの知見が蓄積されている今、「需要予測を核にマーケティング活動全体を改善する」という取り組みが始まっています。今回は、商品・サービスに関する「需要予測」の可能性について、さまざまな角度から解説します。
需要が増えるタイミングが分かれば、マーケティング効率はアップする
「マーケティングコストを投下するなら、最適なタイミングで投下したい」というのは、全てのマーケターの願いではないでしょうか。『エスキモーに氷を売る ―魅力のない商品を、いかにセールスするか』という有名なマーケティングの書籍にあるように、商品やサービスの売り上げを上げるためには、適切なターゲットに適切なタイミングや適切な場所でアプローチをすることが重要です。なるべく需要が喚起できそうな人やタイミングを探索し、獲得効率を高めていこうとする努力は、全ての企業が取り組んでいることでしょう。
さて、世の中には「需要が高まるタイミング」が明確に分かっている商品やサービスもあります。例えば、「バレンタインデーの前にはチョコレートが売れる」「クリスマスの前にはおもちゃが売れる」というようなケース。このように、歳時やイベントのタイミングが固定されている場合は、そこで必ず特定商品の需要が高まるので、集中してマーケティングやプロモーションを仕掛けて売上を最大化する、という取り組みがなされています。
しかし一方で、「ある要因によって需要が上下することは分かっているが、それがいつ起こるかは分からない」という商材もたくさん存在します。「気温が上がると冷やし中華が売れる」「気温が下がるとおでんが売れる」というようなケースはその一例で、現象としては予測できるものの、そのタイミングはあらかじめつかむことができません。そこで多くの企業は、「大きな意味での季節性」としてこうした需要変動に対応し、マーケティングプランを立てるのがこれまでの状況でした。
このほかにも、気象や気温によって需要が左右される食料品や生活消費財は、非常に多く存在しています。そうした商品・サービスのために、気象要因を核とした需要予測にチャレンジし、誕生したのが、ソリューション「ウレビヨリ」です。
気象データや購買データを組み合わせることで、需要予測モデルを構築

「ウレビヨリ」は、一般財団法人日本気象協会と株式会社 電通が共同で開発したソリューションです。日平均気温・日照時間・降水時間・湿度など、日々更新される全国の気象予報情報を常時反映し、エリア別・品目別といった視点で、需要の変化を最長2週間前に捉えることが可能です。そのため、生活者の「今欲しい!」「今必要!」というモーメントを事前に予測することができ、テレビプラニングやデジタル広告配信において、結果として効率が高く機会を逃さないマーケティング施策が見込めます。
「ウレビヨリ」が対象にしているのは、スポーツドリンクや制汗剤など、生活消費財を中心とする約160品目です(2020年10月現在)。さらに、「ウレビヨリ」で培った実績を踏まえて、気象データ以外のデータも分析対象に加えるアプローチを模索。そうして開発されたのが、需要予測の精度を高めるとともに、企業のマーケティング活動を包括的に支援する「ミチシロウ」です。
「ミチシロウ」は気象データに加え、購買データ・広告出稿データ・テレビ番組データ・SNSデータ・その他のユニークな時系列データといったバリエーション豊かなデータを用いて、予測モデルを作成。そこで得られた予測を元に、広告販促、生産・物流などのサプライチェーンマネジメント(SCM)、仕入れ・品揃えをはじめとした店頭施策などマーケティングの全領域において、売上拡大やコスト削減に向けた見通しを提供するコンサルティングサービスです。
需要予測を核におけば、企業のビジネスアクション全体を改善することができる
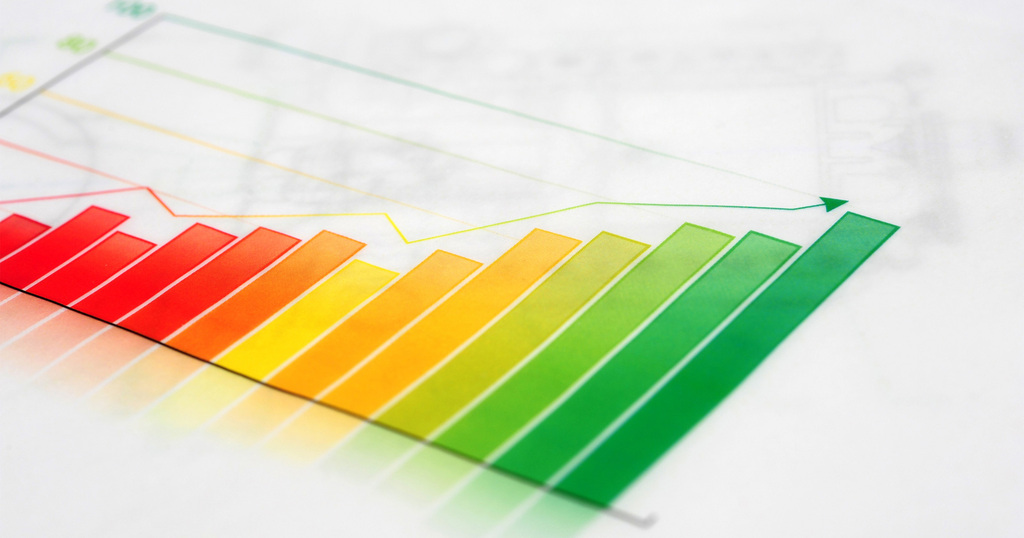
需要予測ができると、マーケティング活動全体が大きく変わります。それは具体的にどういうことでしょうか?需要が上がるタイミングが事前に分かれば、いつどこでプロモーションや広告を展開すれば効率的かが分かりますから、機会獲得をより確実なものにできます。しかし、需要予測がもたらす成果は、それだけではありません。例えば以下に挙げる3つの点において、改善が見込まれます。
1.お客さまのインサイトを発掘
需要の変化を追いかけることで、その背景にあるお客さまのインサイトを発掘することが可能に。需要を左右する要因をつかむことができれば、マーケティング戦略全体を精緻化することができます。
2.生産計画と物流体制のスリム化
需要予測ができれば、生産計画も変わります。つまり需要に応じた生産体制を組むことで在庫などの無駄がなくなり、物流体制も適切に整えることができるのです。
3.魅力的な店頭展開
需要予測ができれば、店頭展開も変わります。需要が高まることが分かっていれば、それに応じた店頭施策を打つことができ、お客さまにとってより魅力的な店頭へとバージョンアップすることが可能です。
このように、需要予測の効果は広告販促にとどまらず、マーケティング戦略から生産・物流、お客さまとの接点である店頭づくりに至るまで、企業活動におけるさまざまな領域に変化をもたらします。
これまで多くのマーケターは、過去の経験則に頼りながらマーケティングプランを立てていたのではないでしょうか。今回ご紹介した需要予測ソリューションは、テクノロジーの進化が可能にした予測モデルによるものですが、決して人間の経験則に基づいたマーケティングを否定するものではありません。なぜならこうしたツールでは、「こういう予測が出たときは、こんなアクションを起こすと効果的」というノウハウを得られるようになるには、予測値と現実を対比させながら何度も試行錯誤を繰り返し、時間をかけてじっくりと精度を高めていく工程が不可欠だからです。
そこで必要になるのが、経験豊かなマーケターの存在です。データから導かれる需要予測を彼らが扱えば、経験に裏打ちされたさまざまな気づきや発見を得ることでき、マーケティング活動の改善の質をいっそう高めることが可能になるのです。
データに基づいた需要予測によって得られる効果を、企業活動全体の視点で解説してきました。もしあなたが、「ライバル企業は需要予測を取り入れることで効果を出した」という情報をキャッチしたら、相手は、準備期間も含めるとかなり前から需要予測に取り組んでいたと言えるでしょう。今後、マーケティングの精度を高めていくために、貴社も早い段階から需要予測ソリューションの活用を検討してみてはいかがでしょうか。











