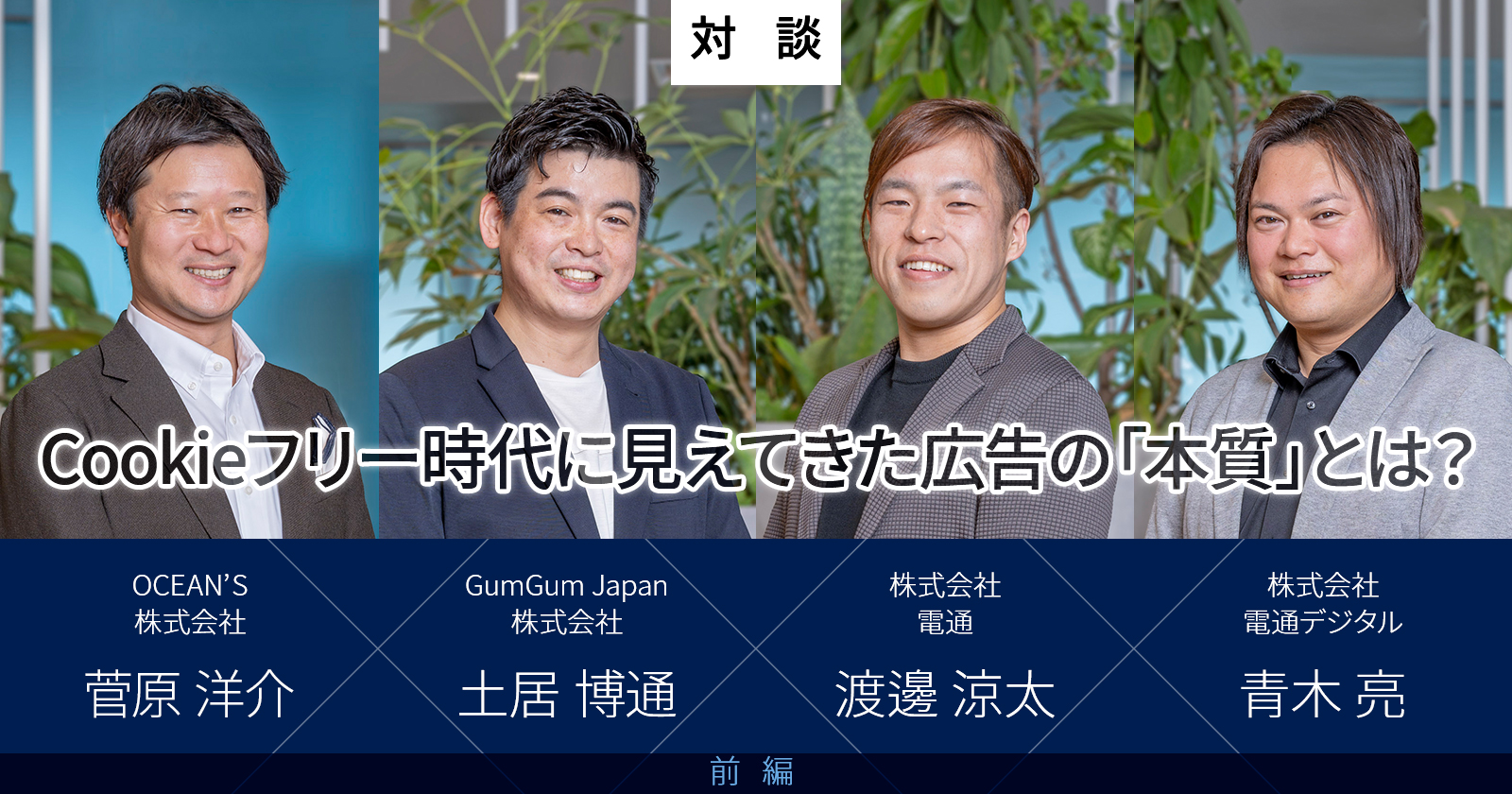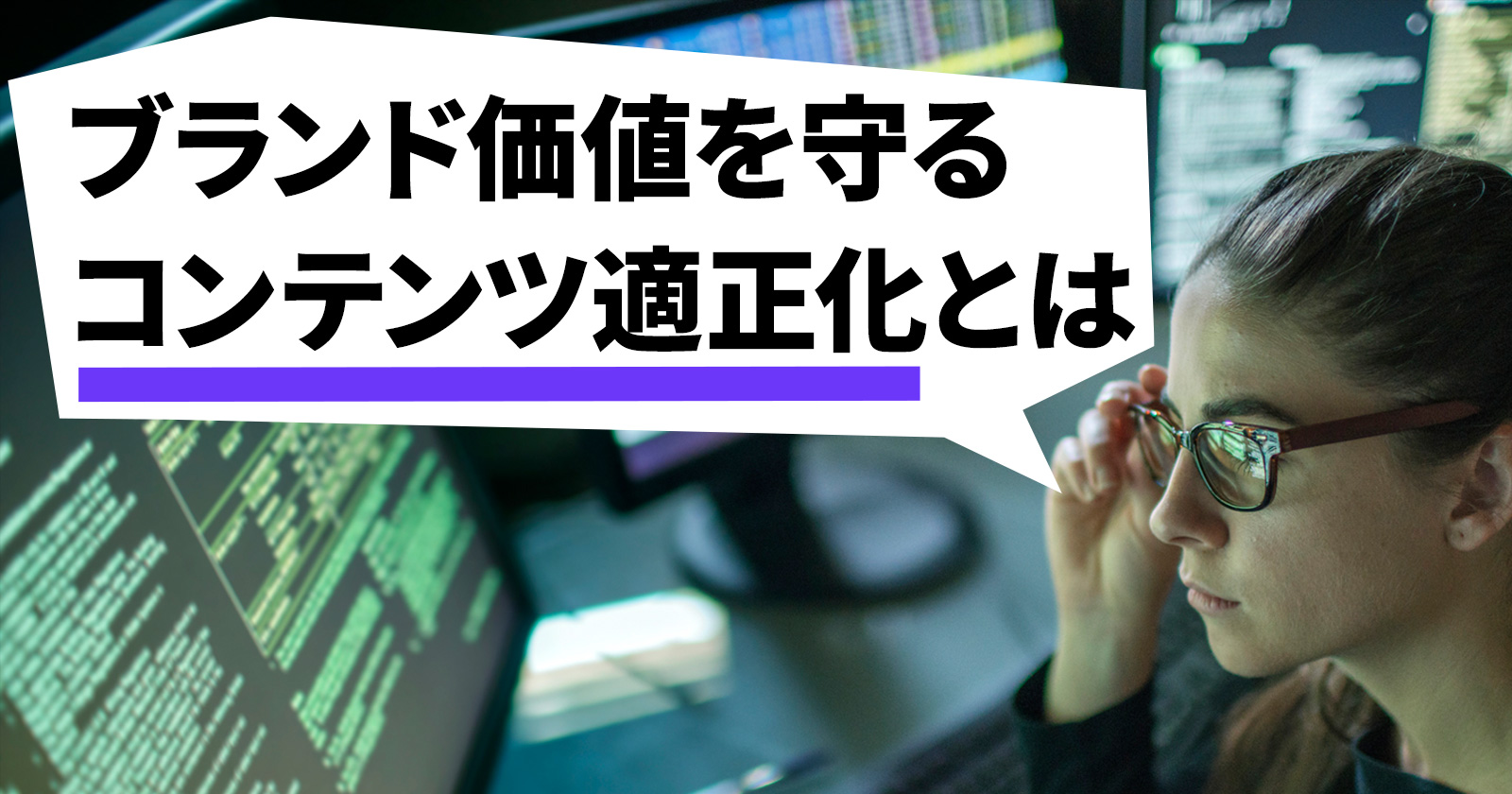Google提唱のサードパーティCookie代替手段「Privacy Sandbox」
Privacy Sandbox
「Privacy Sandbox」は、サードパーティCookieの代替案として、Google社が提唱している新しい概念を指します。これまでCookieによって実現していたトラッキングや広告効果測定などを別の方法に置き換えて広告効果の最大化を狙いつつ、ユーザーのプライバシー保護も両立させようという取り組みです。一口に「Privacy Sandbox」と言ってもさまざまな技術があり、APIごとに機能が異なります。例えば、ターゲティングの代わりとして期待されるTopics APIは、ユーザーの閲覧情報から選ばれた関心の高い項目(トピック)に基づきデジタル広告が配信されますが、トピックの選定をユーザーのデバイス上だけで実行することにより、第三者からのアクセスを防ぎます。ほかにも既に30以上の技術が提唱されており詳細の把握は容易ではありません。広告主やエージェンシーが連携し対応する必要がありそうです。
Transformation SHOWCASEで扱っている Privacy Sandbox に関連する記事はこちら
デジタル時代におけるチラシのポテンシャル。「チラSeeCycle」が変えるメディアプランニングの形 豊富なキャリアを生かし、データに基づくマーケティング施策を提案(前編)|データアナリスト座談会 vol.3Cookie規制対策の切り札となるか。「ユニバーサルID/共通ID」
ユニバーサルID/共通ID
同じくCookie規制に向けた対応策の1つが「ユニバーサルID/共通ID」です。サードパーティCookieに代わるユーザー識別子を生成するソリューションで、識別子を時間が経っても変わらないように設計することで、長期間にわたるユーザーの動向や関心の把握を可能にします。「ユニバーサルID/共通ID」はさらに「確定ID」と「推定ID」の2つに分けられます。「確定ID」は、ユーザーの同意の下で得られたメールアドレスなどの確定データを基に生成するIDで、確定データをキーとしているため、精度が高いのが特徴。一方、「推定ID」はユーザーの行動やデバイスの種類など、個人を特定できない複数の情報を基に、似たような行動をするユーザーに割り振るIDで、量を確保できる点がメリットです。複数の企業が開発を進めており、デジタル広告業界で活用され始めていますが、汎用性の面では課題が残ります。今後の動向に注目しましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている ユニバーサルID/共通ID に関連する記事はこちら
ゼロパーティデータを活用したロイヤルティマーケティング ラコステ、JTB、Vans、THE NORTH FACE、米国Starbucksの事例に学ぶ 越境ECの現状と今後の可能性。 参入のポイントも考えるポストCookie時代に向けて。再び注目を集める「コンテキスト広告」
コンテキスト広告
「コンテキスト広告」もサードパーティCookieの代替案の1つです。Webページ内の文章や画像を解析し、その記事の文脈(コンテキスト)に沿った広告を表示する手法を指します。目新しいものではありませんが、Cookieを活用したターゲティング広告が難しくなると予測される中で再び注目を集めています。個人を狙い打つ「人」を対象とした広告から、Webページや動画、アプリを「面」で訴求する従来の広告手法への回帰としても捉えることができるでしょう。「コンテキスト広告」は、広告の内容とは関連性の低いページにリターゲティング広告が大量に表示される問題なども回避できることから、ブランディングにおけるメリットもあると考えられています。昨今は、ページの内容を解析するAI技術の発達によって精度が向上し、より適切な配信をすることが可能になっています。Cookie規制への具体的な対応策として、活用してみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている コンテキスト広告 に関連する記事はこちら
ITPやCookie規制で変わるコミュニケーション。プライバシーに配慮しつつカスタマーサクセスを実現するテックタッチ施策とは データを通して、人と社会が見えてくる(前編)|データアナリスト座談会 vol.1本当にインプレッション稼ぎに有効?「1秒動画」にひそむ問題点
1秒動画
「1秒動画」とは、X(旧Twitter)などのSNSで投稿が相次いでいる1秒程度の短い動画のことを指します。普通の動画に加えて「1秒動画」を添付する投稿が、一部ユーザーから閲覧数の獲得に有効と考えられ、広まっているようです。しかし、実際にこうした手法がアルゴリズム上有効なのか、SNSプラットフォーム側からの公式な言及はなく、真偽のほどは分かっていません。「1秒動画」のような、SNSに関連したちょっとした“ハック”は定期的に話題を集めます。確かに一時的に効果はあるのかもしれませんが、小手先のインプレッション稼ぎはユーザーの心証を損ね、ブランド価値を傷つけてしまう恐れもあります。もちろん、プラットフォーム側が対策を講じてくることも考えられます。SNSを使ったマーケティングを行う際は、こうした手法の安易な利用には慎重になるべきといえるでしょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている 1秒動画 に関連する記事はこちら
日々のツイートの工夫が、未来のバズを生む。最新版Twitter運用のコツ(前編) ソーシャルリスニング活用のメソッド。SNSにあふれる声を有効なマーケティング資料に(前編)スマホ中毒からの脱却?米国Z世代が夢中になる「dumb phone」とは
dumb phone
スマートフォンの高性能化に逆らうようにして、アメリカのZ世代の間で流行しているのが「dumb phone(ダムフォン)」です。インターネットに接続できるモデルもありますが、基本的には通話やメッセージなどの最低限の機能のみを搭載した携帯電話のことを指します。その意味ではフィーチャーフォンよりもシンプルな携帯電話といえるでしょう。もともと「dumb phone」のターゲットは中高年でしたが、実際には若者のSNS疲れやデジタルデトックス、ノスタルジー消費といった気分にマッチし、Z世代を中心にヒットする結果となりました。「dumb phone」は、個人情報取得につながるSNSが使えないこと、クレジットカードなどの個人情報を登録する機能がないことなどから、プライバシー保護にも有効とされ、そのことも支持を集める理由の1つになっています。日本でもこうした動きが盛り上がるかもしれません。この先の展開に注目しましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている dumb phone に関連する記事はこちら
Z世代起点のインクルージョンが、DEI&B推進のドライバーに(前編) 「暮らしの変化」を、注目のアイテム・事象からキャッチ。「キザシ発掘ラボ」が捉える消費のキザシ(前編)