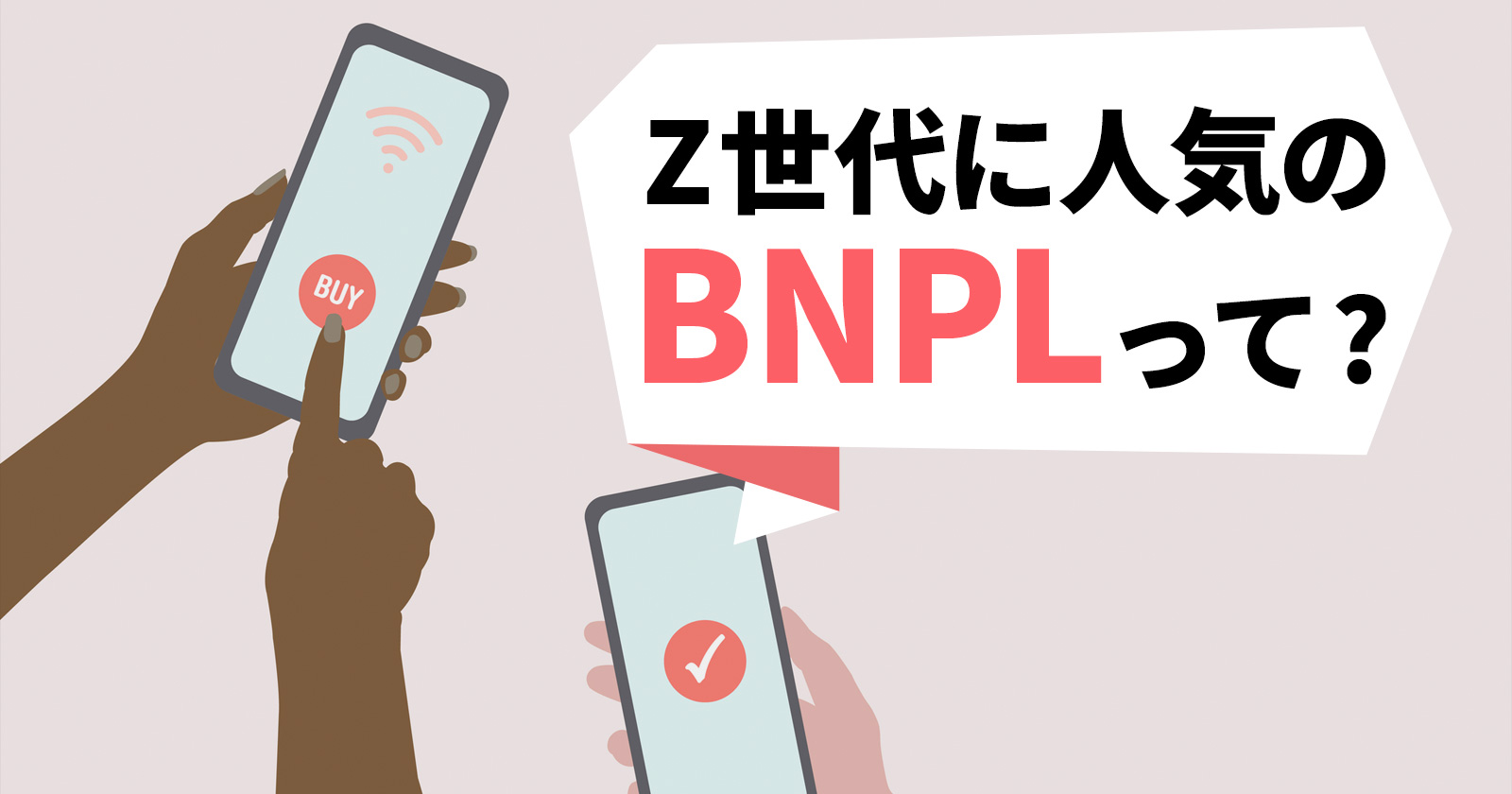パリオリンピック・パラリンピックでもスローガンに掲げられる「クライメート・ポジティブ」
クライメート・ポジティブ
2024年夏季パリオリンピック・パラリンピックのスローガンとして掲げられたことでも注目を集めているのが「クライメート・ポジティブ」です。気候変動やSDGsに関連するキーワードで、温室効果ガスの削減量を排出量よりも多くすることで、地球環境にプラスの効果をもたらそうとする試みのことをいいます。具体的には、再生エネルギーの活用などでCO2排出量を抑えると同時に、森林の保護や再生によりCO2を積極的に吸収することで実現を目指します。近年では、排出量の取引管理にブロックチェーンを活用しようとする新しい動きも盛んになってきました。サステナブルへの意識や環境経営の重要性が高まる中、こうした「クライメート・ポジティブ」の考え方を基にした取り組みは、特に、環境への負荷が高い業界の1つとされるアパレル業界などで進んでいます。この後開催のパラリンピックを楽しみながら、「クライメート・ポジティブ」についても学びを深めてみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている クライメート・ポジティブ に関連する記事はこちら
「カーボンニュートラルに関する生活者調査」結果を読み解く~カーボンニュートラル浸透の現在地と、今後の展望~(前編) ESG経営の効果を可視化する。複雑な問題をAIで読み解く試みとは(前編)日本の食卓を救う切り札に?成長が見込まれる「陸上養殖」のメリット
陸上養殖
「陸上養殖」とは、陸上に人工的に作り出した環境下で行う魚介類の養殖のことです。気候変動や乱獲によって水産資源の減少が問題視される中で、自然環境などの外的要因の影響を受けにくく、魚介類を安定的に供給できる方法として注目されています。海上養殖と比較すると、細菌やウイルスが侵入するリスクが少ない、トレーサビリティが容易で安全性が高い、環境負荷が少なくサステナブル……といったさまざまなメリットがあり、地産地消や雇用促進による地域活性化にもつながると期待されています。設備投資などのコストが高い点が課題ですが、大手・スタートアップ問わず複数の企業が参入し、収益化に取り組んでいます。既にヒラメやサケなどは国内での出荷実績があり、2024年には新たにイワシなどの出荷も開始。スマート漁業や人工飼料などの関連ビジネスとの親和性も高い「陸上養殖」の可能性に着目してみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている 陸上養殖 に関連する記事はこちら
2025年のライフスタイルを予測!『「ありたい、ちょっと先の未来」調査』で見えてきた、「新感覚層」が生み出すトレンド(前編) 「サステナブル時代のまちづくり」を、シンガポールの都市開発、環境デザインから学ぶ。(前編)米国Z世代に見られる「HIFIs」。高収入にもかかわらず経済的に不安定になる要因とは
HIFIs
「HIFIs(High Income Financially Insecure)」とは、高収入を得ているにもかかわらず、経済的に安定していない人々を指します。主に米国のミレニアル世代やZ世代に多く見られ、その原因には自己顕示欲からの浪費や散財、BNPL(後払い決済)の過剰利用などが挙げられます。また、コロナ禍による外出制限中に増えた「巣ごもり消費」を抑えることができず、制限が解除された以降も外出時の出費がそのままプラスされている、といったケースもあります。物価高や雇用の不安定化などによる将来への不安を解消するために、消費に走る人も少なくありません。「HIFIs」という言葉は米国発ですが、日本でも円高の影響を受けながら、SNSで自己をよく見せようとすることで出費を重ねる人がいます。「HIFIs」の影響は多岐にわたるため、今後も注目すべきキーワードと言えるでしょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている HIFIs に関連する記事はこちら
Z世代ならではの購買体験をプランニング。「若者消費ラボ」が目指す未来とは(前編) 「暮らしの変化」を、注目のアイテム・事象からキャッチ。「キザシ発掘ラボ」が捉える消費のキザシ(前編)誰もがパーソナライズされたAIを職場に持ち込める?「BYOAI」の時代
BYOAI
大手IT企業の予測が発端となり注目されているのが「BYOAI」です。「Bring Your Own AI」の略称で、誰もが共通のAIを使うのではなく、個々にパーソナライズされたAIを職場に持ち込んで使うことを意味します。プロンプトエンジニアリングという領域が成り立つことからも分かるように、生成AIの有効活用にはある種のテクニックが必要ですが、個人に最適化されたAIであれば、データ分析やリサーチなどに活用しやすく、成果も得やすいと期待されています。また、セキュリティーの観点から外部のAIサービスを業務で利用することを禁止する企業も多く、その対応策として自社独自のAIを使おうとする動きなども「BYOAI」の促進に結びつくと考えられています。日本では職場へのAI導入率が10%を超えるという調査もあり、「BYOAI」の一般化もそう遠くないかもしれません。引き続き、AI関連のトレンドをキャッチアップしていきましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている BYOAI に関連する記事はこちら
AIビジネスの現場から語る「生成AIは、マーケティングやコミュニケーションをどのように変えるのか」(前編) DX時代のAIを乗りこなすために~マーケティングにおけるAI活用の潮流と可能性~電車に自転車を持ち込んで移動を。地域活性化にもつながる「サイクルトレイン」
サイクルトレイン
「サイクルトレイン」とは、自転車を解体したりせず、電車内にそのまま持ち込むことができるサービスです。鉄道と自転車を組み合わせることで行動範囲の拡大、公共交通機関の利用促進につながり、特にローカル線活性化の一施策として注目が高まっています。コロナ禍を経て人気が高まるサイクルツーリズムやウェルネスツーリズムといった観光をモビリティ連携で後押しするほか、エコな乗り物である自転車の利用を促す点でサステナブルな取り組みとしても効果的です。最近は、地域の交通手段としての利便性を高めるべく、通勤通学に「サイクルトレイン」を活用する実証実験も始まっています。このように「サイクルトレイン」は、大きなコストをかけることなく、地域活性化や社会課題解決などの複合的な効果を期待できます。全国的に導入事例が増えていますが、まだまだ拡大の余地があり、ビジネスとしても大きなポテンシャルを秘めた領域といえるでしょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている サイクルトレイン に関連する記事はこちら
地方創生はSDGsから。高知での取り組み「Kochi SDGs Action」の現在地とこれから(前編) DIで進化するB2Cグロース戦略を、コロナ禍の「鉄道業界」を例に考える(前編)