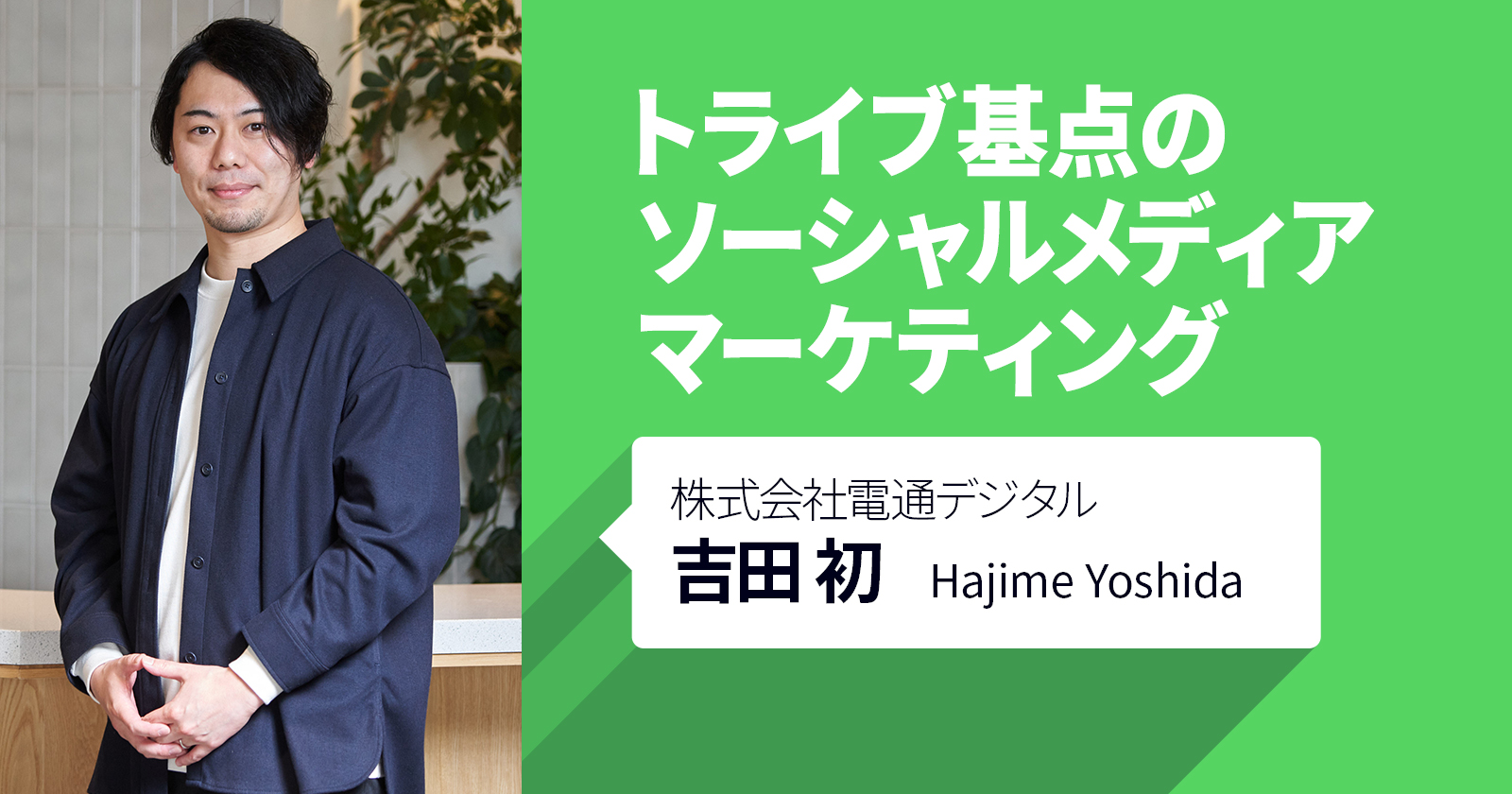ビジネスケアラーの増加など、経済への影響も大きい「2025年問題」
2025年問題(ビジネスケアラー)
「2025年問題」とは、約800万人いるとされる団塊の世代全員が75歳以上の後期高齢者になることによって生じるさまざまな問題のことで、特に注目を集めるのが働きながら家族などの介護をする「ビジネスケアラー」の増加です。2023年の経済産業省の資料によると、2030年には「ビジネスケアラー」は300万人以上に達すると推計されており、その数は家族介護者全体の約4割に及びます。また、介護のために仕事を辞める介護離職や介護の負担による労働生産性の低下が原因で生じる経済的損失は約9兆円に上るとの試算もあります。こうした損失を防ぐため、企業には、リモートワーク導入などの働き方改革やDXの推進など、「ビジネスケアラー」の負担を軽減する環境整備を積極的に行うことが望まれます。超高齢社会の中で、医療や福祉といった社会保障の負担の増大が予想される中、「ビジネスケアラー」への支援は社会全体で進めるべき取り組みといえるでしょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている 2025年問題(ビジネスケアラー) に関連する記事はこちら
「障がい者雇用」がもたらすもの~パラスポーツのトップランナーが導く共生社会~ AIが社員の健康を守る?表情分析AIでリモートワーカーの感情変化を把握。「INNER FACE™」は、人とビジネスの関わり方をどう変えるのか(前編)シニア世代とSNSの新しい関係性を象徴する「インスタグランマ」
インスタグランマ
人生100年時代といわれる中、シニアマーケティングにも新しい価値観や考え方が生まれています。SNSを使いこなすシニア世代の女性を指す「インスタグランマ」もそのうちの1つで、シニア向けビジネスを扱う企業が新たなトレンドとして発表したことで注目を集めました。実際、日本のシニア層におけるSNSの利用率は30%以上ともいわれているように、SNSを開くと、おしゃれなファッションや日常生活を発信し、年齢にとらわれず自分のスタイルやライフスタイルを積極的に共有している「インスタグランマ」は、今や珍しくありません。海外では数十万人のフォロワーを持ち、インフルエンサーとして活躍している「インスタグランマ」もおり、今後は彼女たちがビジネスパートナーとなる機会も増えてくるかもしれません。消費者としても、ビジネスパーソンとしても、存在感を高めているシニア層との向き合い方をあらためて考えてみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている インスタグランマ に関連する記事はこちら
人生100年時代をより良く暮らすために。人と生活研究所が進める「これからのウェルビーイング」(前編) 女性の課題を解決するテクノロジー「フェムテック」の現在地居心地が良いだけでは不満? Z世代の就職観が見える「パープル企業」とは
パープル企業
「パープル企業」とは、過度な残業やハラスメントなどがなく、居心地の良い職場環境である一方で、業務内容が単純で変化に乏しい、ルーティンワークが多いといったマイナスな要素を含む企業を指します。「ブラック企業」に準じる否定的なニュアンスで「ゆるブラック企業」とも呼ばれ、成長できない環境として、特にZ世代から忌避される傾向があります。将来に対する不安が強く、タイパを重視して「効率的に成長して市場価値を高めたい」と考える人が多いZ世代にとって、働きやすさやワークライフバランスだけでなく、仕事を通じて新たなスキルの習得や成長の実感が得られるかどうかも就職先を選ぶ上で重要な判断材料になっているようです。成長意欲のある優秀な人材を確保するためにも、企業の採用や育成担当者はZ世代のこうした心理を理解し、彼らにとって魅力的な環境作りやブランディングを実現していく必要があるのかもしれません。
Transformation SHOWCASEで扱っている パープル企業 に関連する記事はこちら
「タイパ」はコンテンツをどう変える?Z世代の実態から考える、これからのクリエーティブ(前編) Z世代起点のインクルージョンが、DEI&B推進のドライバーに(前編)米国Z世代に見られる「破滅的消費」。日米の消費動向の違いを比較
破滅的消費
「破滅的消費」は、アメリカのZ世代に見られる、「今」を楽しむための身の丈に合わない過度な消費行動を指します。高価なブランド品やぜいたく品の購入などによる浪費行動がその典型例です。前回ご紹介した「HIFIs」にも似ていますが、「HIFIs」は収入が安定していながら、自己顕示欲の充足などを目的に浪費行動をとる人々を指すのに対し、「破滅的消費」は将来に対する不安や現在の経済状況に対する悲観といった心理を背景に、お金の有無にかかわらずとってしまう浪費行動という点に違いがあります。一方、日本のZ世代に目を向けると、アメリカと同様に経済的な不安感は高まっているものの、むしろ過度な倹約に傾く人が多く、その消費動向は対照的です。とはいえ、SNSによる影響などを受け、今後国内でも「破滅的消費」のような新たな動きが起こらないとは言い切れません。他国の状況と比較しつつ、日本のZ世代の動向に注目しましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている 破滅的消費 に関連する記事はこちら
BNPLはZ世代になぜ人気?後払いの新しい決済スタイルとは。魅力的なCXのヒントにも ハイブランド・マーケティングのプロに学ぶ、コロナ禍で変化した新富裕層の消費トレンド防御側が先手を取るセキュリティ対策。政府が進める「能動的サイバー防御」とは
能動的サイバー防御
「能動的サイバー防御」とは「Active Cyber Defence」の和訳で、不正アクセスなどのサイバー攻撃を未然に防ぐセキュリティ対策のことです。昨今、懸念が高まっている国の重要インフラを狙ったサイバー攻撃への効果的な防御策として注目されています。「能動的サイバー防御」では、民間の通信事業者から取得した通信データを分析し、ネットワークを平時から監視。怪しい動きを検知した際には、攻撃元のサーバーに侵入して被害が発生する前に無害化します。しかし、こうした監視強化は憲法が定める通信の秘密の侵害に当たるとの指摘もあり、政府は導入に向けた法整備を検討しています。さらに対処能力の向上のため、通信データを米国と共有することも視野に入れていますが、プライバシー侵害や情報漏えいなどの課題は残ります。実現すればセキュリティ対策の在り方が大きく変わる「能動的サイバー防御」。今後の動きを注視しましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている 能動的サイバー防御 に関連する記事はこちら
Web3.0時代の到来で何が変わる?デジタル社会の変革で生まれる新たなビジネススタイルとは 内閣府推進の防災4.0に見る、防災DX。「防ぐ・支える」ソリューションに学ぶ、企業DXの進め方