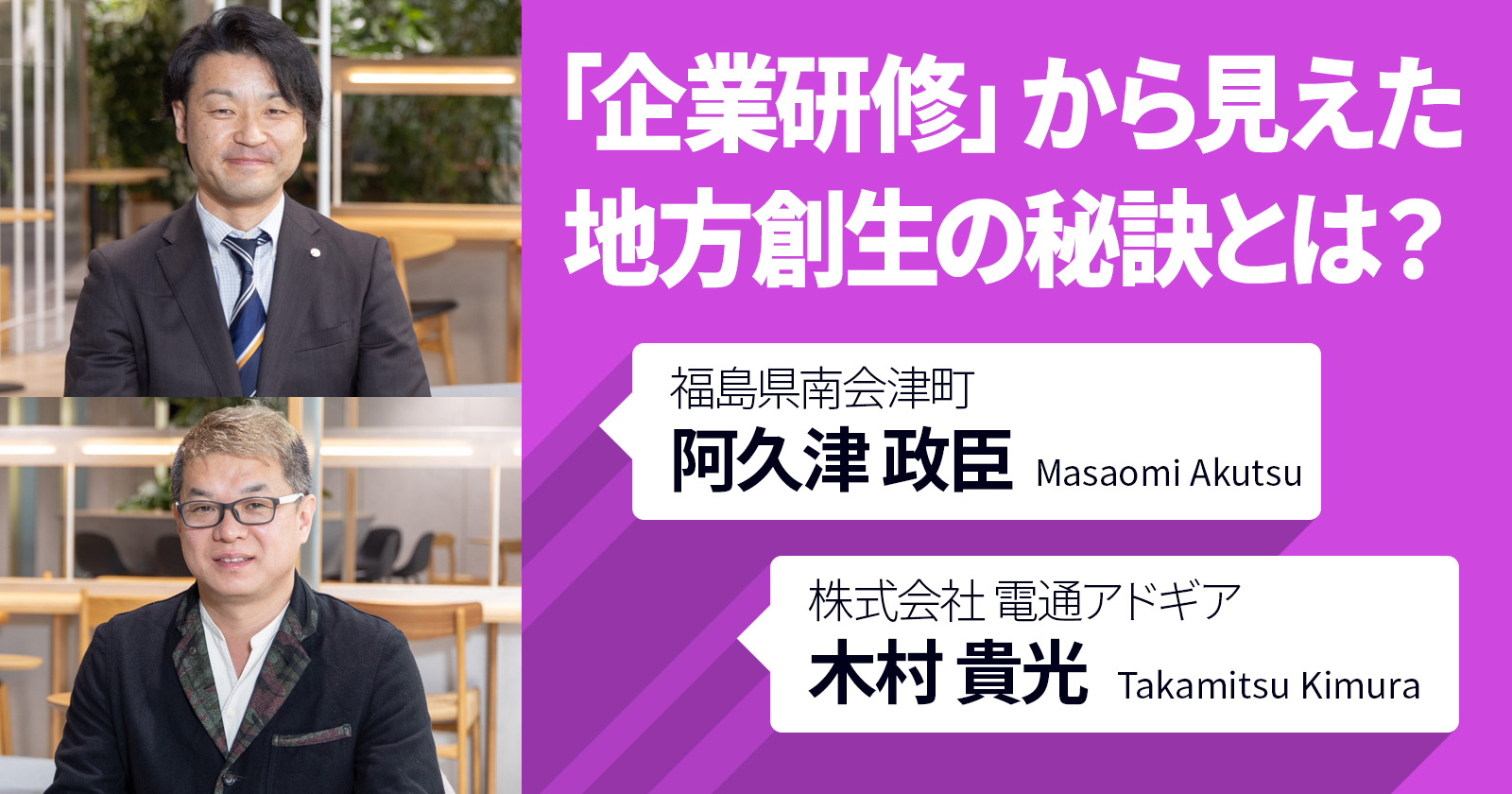生成AIをより実用的に。人間のフィードバックによる強化学習「RLHF」
RLHF
AIの活用が急速に広まり、XAI(説明可能なAI)やAGI(人工汎用知能)といったより高度な技術や概念が話題になる一方、AIが事実に基づかない情報を生成してしまう「ハルシネーション」など、負の側面も指摘されています。そんな中、ChatGPTにも採用され、注目を集めているのが、「RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)」。AIモデルの出力の精度を改善する試みの1つで、「人間のフィードバックによる強化学習」を意味します。人間が用意したプロンプトとそれに対する望ましい応答をセットにして学習させることなどで、人間の好みや価値基準を反映。AIの受け答えを倫理面にも配慮された、より安全なものへと改善します。こうした注目ワードを理解しながら、進化を続けるAIについて最新の情報をキャッチアップしていきましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている RLHF に関連する記事はこちら
AIが社員の健康を守る?表情分析AIでリモートワーカーの感情変化を把握。「INNER FACE™」は、人とビジネスの関わり方をどう変えるのか(前編) データ起点でビジョンを描く。データストラテジーに基づくAI・機械学習ソリューションとは(前編)AIの進化で急増。Web広告の信頼性を揺るがす「MFA」
MFA
かねてより、広告収入を不当に稼ぐアドフラウドのような不正行為が大きな問題となっているWebの世界。最近、新たな懸念としてアメリカを中心に議論が過熱しているのが「MFA(Made For Advertising)」です。広告収益のみを目的とし、ユーザーにとって価値の低いコンテンツを配信するWebサイトの総称で、生成AIによってWebサイトの作成が容易になっていることも、問題に拍車を掛けています。自動再生動画や興味をかき立てる見出し・サムネイルでリンクを踏ませる手法などで、多くの広告費を引き出そうとします。低品質なコンテンツが多く、ユーザーには迷惑な存在であり、広告主にとっても広告費を無駄に消化してしまう厄介な存在。サイトの作りが巧妙なので自動検出できず、数が多いので手作業で排除もできず、問題の解決は一筋縄ではいきません。マーケティングの観点からも、動向を注視し、対応策を模索する必要がありそうです。
Transformation SHOWCASEで扱っている MFA に関連する記事はこちら
企業のソーシャルメディア活用に次なる一手を。アドとオウンドをつなぐ「Social Connect Group」の役割(前編) AIでクリエーティブは無限に?「AI」×「人間のアイデア」で生み出す、これからのクリエーティブ(前編)インバウンド誘客にも有効?ニッチな市場で行動喚起する「ナノインフルエンサー」
ナノインフルエンサー
「インフルエンサー」というと数万~数十万人ものフォロワーを抱えた有名人をイメージするかもしれません。一方、今回ご紹介する「ナノインフルエンサー」はフォロワー数が1,000~1万人程度のインフルエンサーを指します。大量のフォロワーを抱える「マクロインフルエンサー」と比べて相対的にフォロワーが少ないため、ユーザーとの距離が近く、コミュニティーを形成しやすい、ニッチなトピックに強いといった特徴があります。また、エンゲージメント率が高く、購買などの行動喚起につながりにくい市場に対するマーケティング施策として効果的と考えられています。例えば最近は、観光客の呼び込みなど、地域活性化を目的とした施策に地元の「ナノインフルエンサー」を起用するケースも。認知から行動へとつなげるマーケティング施策として、「ナノインフルエンサー」の活用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている ナノインフルエンサー に関連する記事はこちら
興味関心・ライフスタイルでSNSユーザーをグループ化。「Tribe Driven Marketing」に見るSNSデータ活用最前線(前編) Z世代ならではの購買体験をプランニング。「若者消費ラボ」が目指す未来とは(前編)「オーバーツーリズム」の改善策になるか?「アンダーツーリズム」に期待
アンダーツーリズム
インバウンドの増加に伴い、問題となっている「オーバーツーリズム」。その改善策とも言えるのが、「アンダーツーリズム」です。あまり認知度が高くなく、観光客の少ないローカルエリアを訪れたり、早朝や平日など人が少ない時間帯を狙ったりして、密を避ける観光を指します。メリットとして、混雑の緩和、地元住民の生活負担の軽減、地域の新たな魅力の発掘などがあります。海外では、例えば、ノルウェーの首都・オスロが博物館やレストランを混雑なしで楽しめることをアピール。コロンビアで「危険な街」として知られるメデリンも「アンダーツーリズム」で再生を図っています。日本でもその有効性が浸透し始めており、オーバーツーリズムが深刻な京都では隠れた名所の発信などで観光客の分散を促進。愛知県佐久島でも「癒しとアートの島」として新たな体験価値を発信するなど数多くの事例が見られ、これからの観光ビジネスのヒントになりそうです。
Transformation SHOWCASEで扱っている アンダーツーリズム に関連する記事はこちら
DIで進化するB2Cグロース戦略を、コロナ禍の「鉄道業界」を例に考える(前編) マイクロツーリズムで獲得した新規顧客をリピーターに。他業種にも応用できるLTV向上施策とは地域活性化の次なる一手に。「デジタル地域通貨/地域ペイ」の可能性
デジタル地域通貨/地域ペイ
地域活性化の一環として「デジタル地域通貨」、通称「地域ペイ」を発行する自治体が増えています。2000年代初頭にも紙媒体での地域通貨が流行しましたが、デジタル運用によるコストの削減、保有・利用状況のデータの可視化、そのマーケティングへの利活用といった新たな利点により、テクノロジーの進化とともにビジネスモデルを変えながら、再び拡大しています。近年では、ふるさと納税の返礼品として地域通貨を付与して域外からの集客を図るといった施策も見られるようになりました。ユーザー視点では、アプリ上でのポイント付与や連携、地域経済への貢献などもうれしいポイントです。導入コストや、他のキャッシュレス決済の競合が多いといった課題もありますが、数億~数十億円規模の発行を行う成功事例も生まれています。まずはユーザーとして体験しつつ、地方創生を図るビジネスの次なる一手として活用を考えてみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている デジタル地域通貨/地域ペイ に関連する記事はこちら
金融の枠組みを超えて地域産業を振興。九州みらいCreationがつくる地域の未来(前編) 海外のスーパーアプリ成功例から見る、日本市場における可能性とは