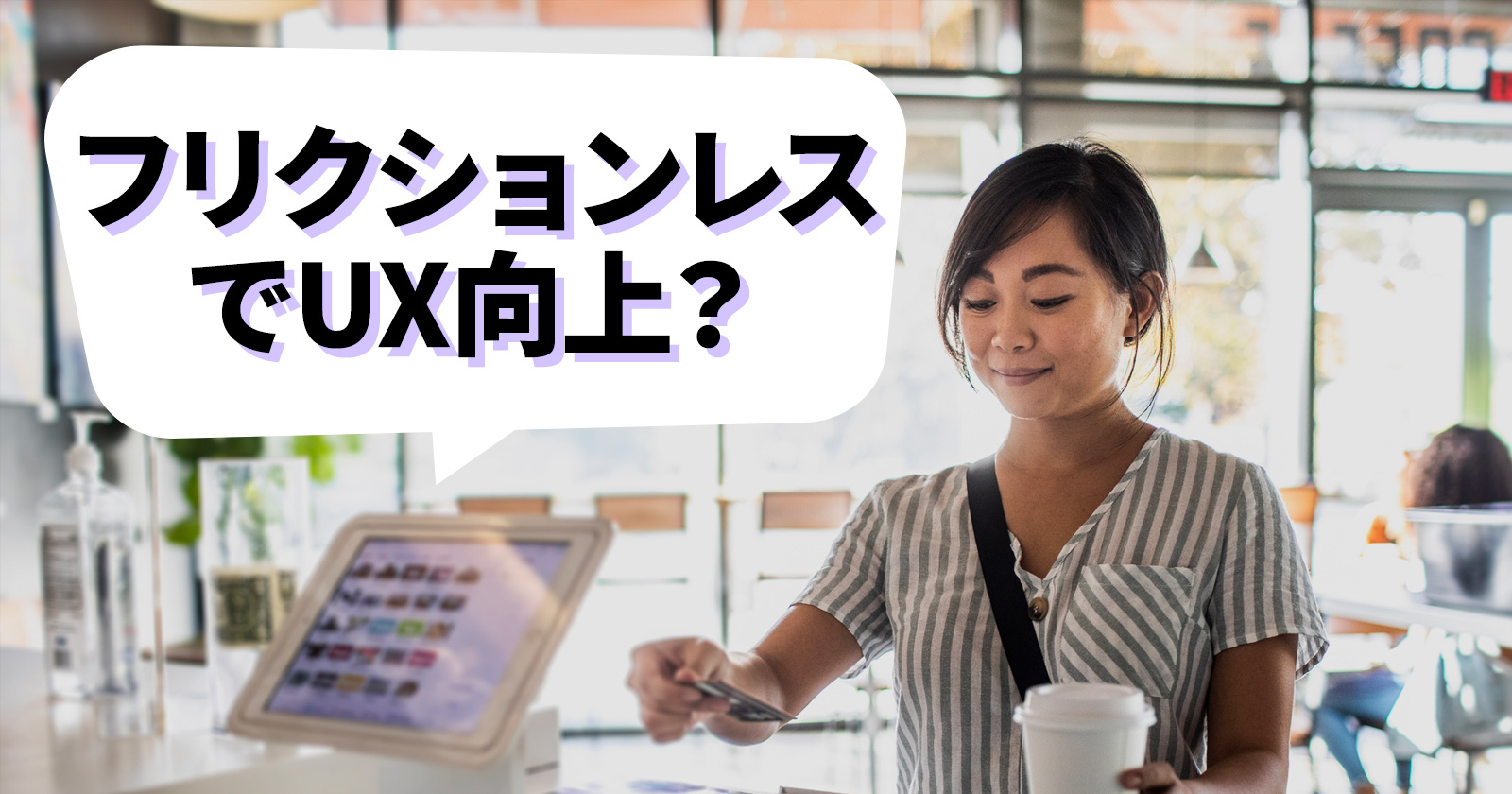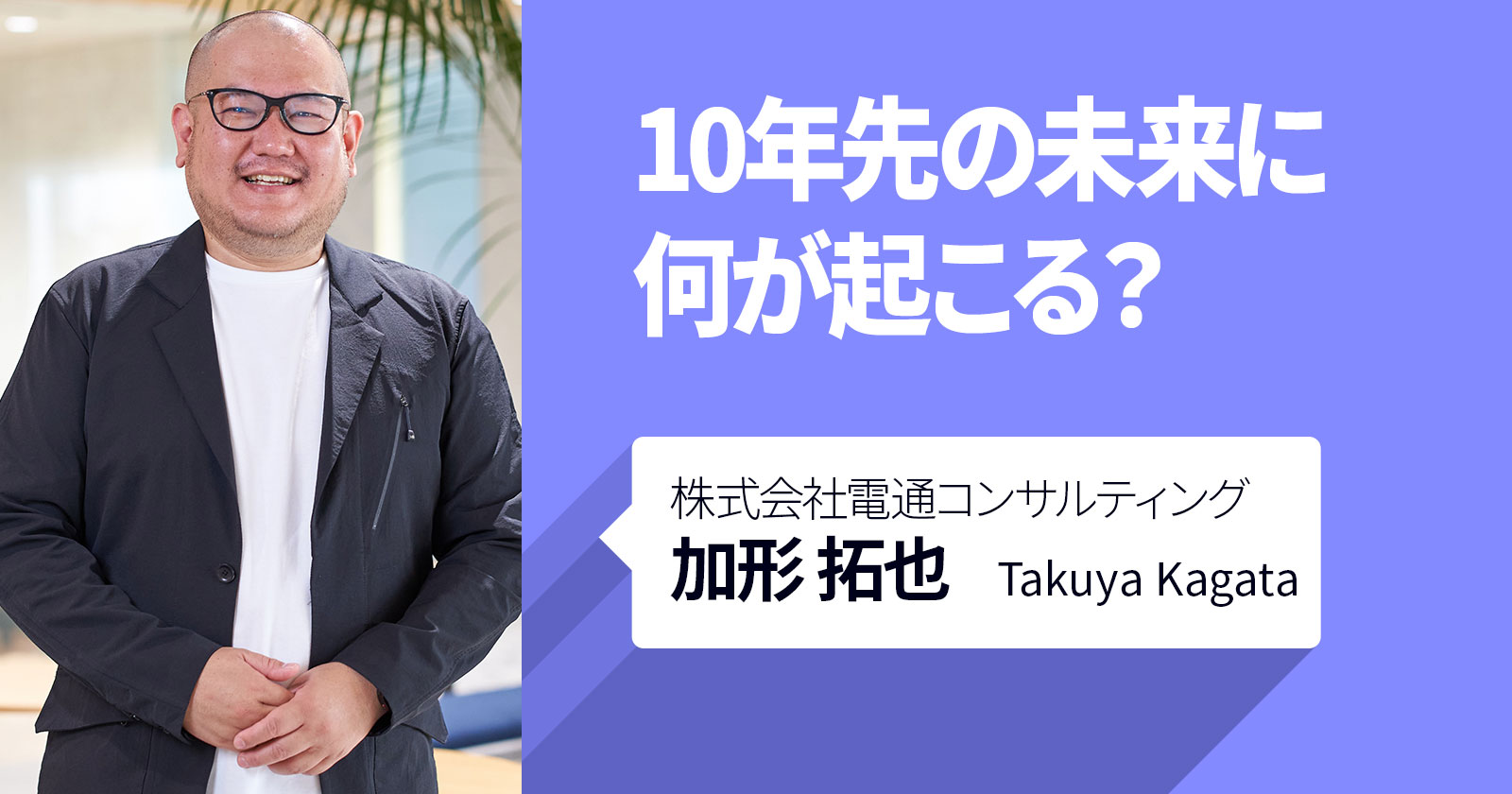注目集まる「デジタル給与」。決済ビジネスの潮目を変えるか
デジタル給与
キャッシュレス決済の普及を狙いの1つとして、2023年4月の法改正で解禁されたのが「デジタル給与」です。これによって従業員への給与の支払いが、電子マネーや決済アプリなどを使って行えるようになりました。法改正にあたっては、デジタル給与の強制の禁止、現金化できないポイントや仮想通貨の使用の禁止など、ユーザーが不利益を被らないよう配慮がなされているものの、口座を不正利用されるリスクや企業側の運用負担の増加などの課題も指摘されています。まだ普及しているとは言えない状況ですが、電子マネー事業者がスポットワーク事業に参入し、「将来的にデジタル給与払いを実現する」と発表したことを受け、注目度は高まっています。こうした動きが拡大すれば、キャッシュレス決済の利用シーンやユーザー層も変化していくことが予測されます。さまざまなビジネスに影響を与え得る「デジタル給与」の今後の展開を追っていきましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている デジタル給与 に関連する記事はこちら
増加し続ける「コンタクトレスエコノミー」とは何か?CX設計の重要性と共に考える DXの時代、ハイスキル・フリーランス人材の活用が企業課題を解決に導く(前編)「V2H」で電気自動車から自宅に給電。EVをもっとサステナブルに
V2H
「V2H/VtoH」とは「Vehicle to Home」の略で、家庭用の電力をEV(電気自動車)などに充電する機能に加え、EVのバッテリーに蓄えた電力を家庭に送るという双方向の給電機能を備えた仕組みのこと。車を蓄電池のように扱うことができるため、停電時などに電源として活用でき、身の回りのものを災害などの非常時に役立てる「フェーズフリー」という考え方や「防災DX」と親和性があります。また、充電スピードが速く、自宅での高速充電が可能。充電スタンド不足の解消にもつながります。太陽光発電と連携することで、より効率的に電力を利用できることから、サステナビリティの観点からのメリットも。2023年10~11月にかけて開催されたジャパンモビリティショーでも複数の「V2H」製品が紹介されました。導入コストなどの課題はあるものの、EVの一般化やサステナブル意識の高まりも相まって、さらなる普及が見込まれます。
Transformation SHOWCASEで扱っている V2H に関連する記事はこちら
電通グループ横断で企業や団体のカーボンニュートラル実現を支援。「dentsu carbon neutral solutions」から始まる脱炭素への道筋(前編) スマートシティで活用が進むデジタルツイン。現実世界をデジタル上に再現する技術がビジネスにもたらす可能性とは?「ECアグリゲーター」がもたらしたD2Cビジネスの光と影
ECアグリゲーター
これまで米国を中心に急速な広がりを見せてきたD2Cですが、近年、そのブームにかげりが見えてきました。「ECアグリゲーター」とは、そうしたD2C企業を中心としたECブランドを買収し、マーケティングやブランディングを改善・強化することで企業価値を高めるビジネスを行う企業のこと。D2Cの盛り上がりとともに、ユニコーン企業となった「ECアグリゲーター」がいくつも生まれましたが、そうした成功は必ずしも長続きせず、最近では著名な「ECアグリゲーター」の倒産も報じられています。決して先が明るいとは言い切れない「ECアグリゲーター」ですが、ECビジネスをめぐる1つの潮流として、自社が時代の変化にどのように対応していくのかを考える上でも、理解を深めてみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている ECアグリゲーター に関連する記事はこちら
プラットフォーム事業社のデータ活用で、デジタル販促はますます進化する。「SP COMPASS」で実現する、効果の最大化(前編) D2CからP2Cへ。個人ブランドの強みを国内の成功事例から考えるIT企業が強化を進める「オファリング」。これからの提案型ビジネスとは
オファリング
近頃、日本のIT企業で増えているのが「オファリング」と銘打ったサービス。「オファリング」はもともと、外資系のコンサルティング会社でよく用いられていた言葉で、サービスやソリューションの提供といった意味合いがあります。IT業界では、顧客に言われたことをなんでもやる、という昔ながらの営業スタイルではなく、ノウハウや知見の伝授、仕組みの導入などを一括して提案するコンサルティング型ビジネスというニュアンスで使われることが多いようです。ただし、明確な定義が存在するわけではなく、各企業がそれぞれの解釈で使っているのが現状。例えば、ある大手IT企業では、さまざまな製品やサービス群を組み合わせたDX事業を「オファリング」と称しています。まずは、コンサルティング業界以外でも使われ始めた「オファリング」という単語を頭に入れつつ、今後の広がり方をチェックしていきましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている オファリング に関連する記事はこちら
データからアクションへ。「DI×グロースコンサルティング」で目指す、次世代の成長戦略(前編) ビジョンドリブンで未来をつくる。「Future Vision Studio」と共創する予測不能時代の未来事業(前編)長引く「ウッドショック」。これからの日本の林業の在り方を問う
ウッドショック
「ウッドショック」とは、2021年前半に木材の価格高騰によって生じた諸問題のこと。コロナ禍にリモートワークが定着し、米国で新築住宅の需要が高まり、木材の買い占めが起こったことが発端とされています。木材需要が一段落した後も、ウクライナ侵攻などの影響も加わり問題は長期化。2021年以前の水準と比べて、価格は高止まりしている状況です。輸入木材に依存している日本でもその影響は大きく、住宅価格の高騰や建築スケジュールの遅延など、さまざまな問題が生じました。現在も住宅業界のみならず、木材を原料にする楽器メーカー、バイオマス発電を行う電力会社など、多くの業界に打撃を与えています。対策として林業の在り方を見直し、国産材を活用しようとする動きも見られますが、完全な収束には至っていません。SDGsの観点からも「ウッドショック」にまつわる問題に今一度、目を向けてみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている ウッドショック に関連する記事はこちら
サステナブル社会に向けた新規事業開発を支援。「Sustainable Future Design プログラム」が作る未来志向の事業(前編) 「サステナブル時代のまちづくり」を、シンガポールの都市開発、環境デザインから学ぶ。(前編)