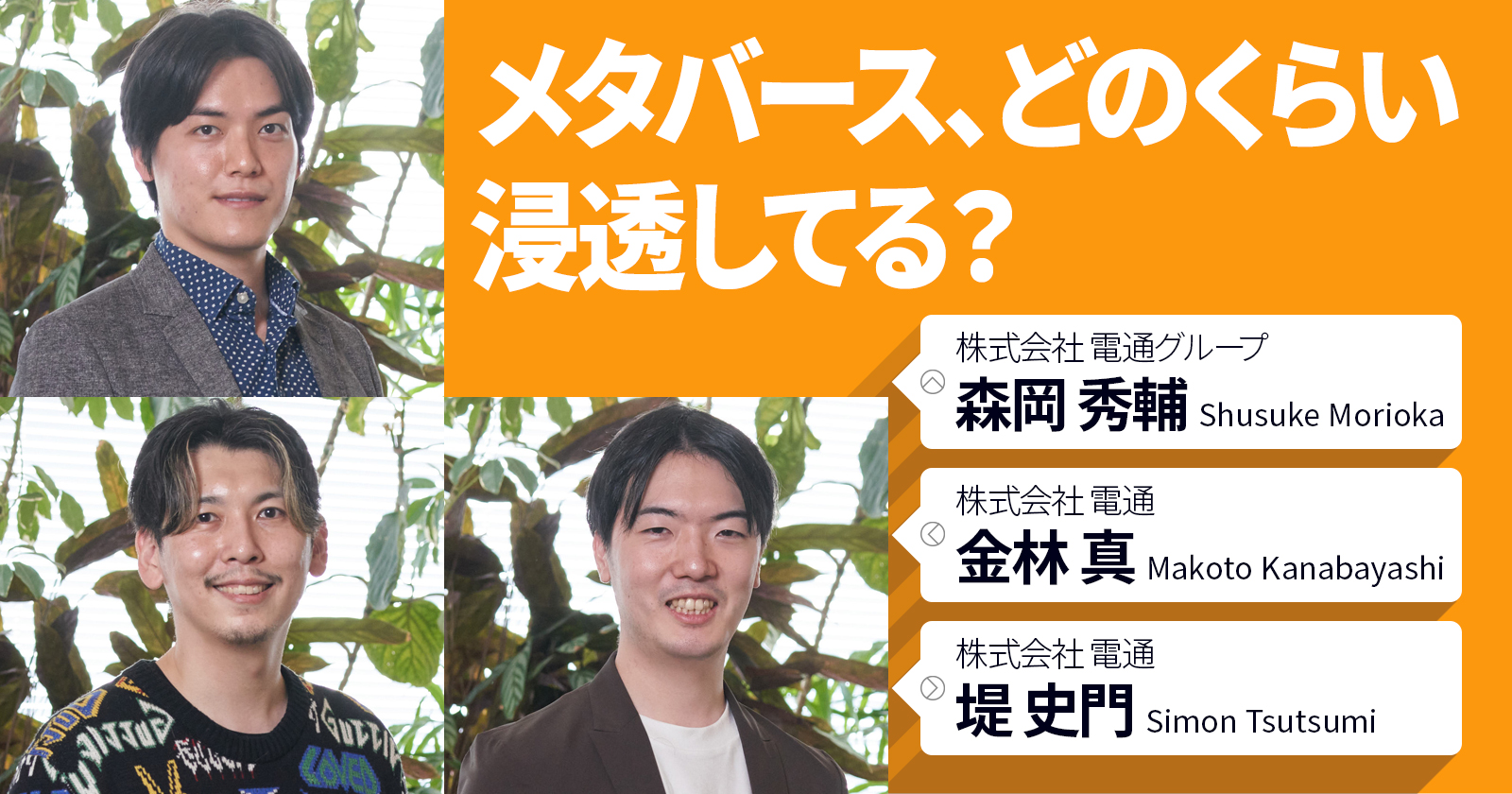人手不足解消に寄与するか。高度なリアルタイム処理が可能な「エッジAI」
エッジAI
「エッジAI」とは、スマートフォンなどのエッジデバイス(ネットワークの末端に接続された機器)に搭載され、クラウドを介さずにデータの処理や意思決定を行うAIを指します。現在主流となっているクラウドAIは、エッジデバイスからデータを送信し、クラウド上で処理をした後、その結果をデバイスに返す仕組みが一般的です。一方、エッジコンピューティングを応用した「エッジAI」は、デバイス内でAIによる処理が可能なため、データの送受信が不要になり、リアルタイム性やセキュリティが向上します。こうした特徴から、最近では自動運転、産業用ロボット、警備業界など、現場での迅速な制御が求められる分野で活用が進んでいます。コストやメンテナンス性といった課題はあるものの、高度な判断を必要とする作業を「エッジAI」が担うことで、深刻化する人手不足の解決策となることも期待されています。今後の技術進化から目が離せません。
Transformation SHOWCASEで扱っている エッジAI に関連する記事はこちら
松浦市と電通九州、NEXT DELIVERYが新スマート物流で挑む「離島の買い物難民」問題(前編) 今、マーケターに求められる力とは。クリエーティブ・プロデューサーから見た、「オン・オフ統合」時代に求められるディレクション購入後にアップデートできる自動車?ソフトウェアが主役となる「SDV」とは
SDV
「SDV(Software Defined Vehicle)」とは、直訳すると“ソフトウェアで定義される車”を意味します。従来の自動車はハードウェアが主体で、購入後の機能アップデートは難しいですが、「SDV」はソフトウェアの更新によって機能を追加したり、自分好みのアプリを入れてパーソナライズできたりするのが特徴です。この仕組みにより、ユーザーは購入後も車の性能を上げることができ、頻繁に買い替える必要がなくなります。また、メーカーは自動運転機能を月額で提供するなど、サブスクリプションによる新たなビジネスを展開することが可能に。コストやセキュリティ面などの課題は残っていますが、多くの企業がソフトウェア開発に参入しており、2026年には一般発売も予定されています。IoTや自動運転技術がカギを握る「CASE」時代の重要なキーワードとして、今後の動向を注視していきましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている SDV に関連する記事はこちら
つながり続ける時代の顧客体験を進化させるシームレスな体験デザインとは 農業ビジネスを変革するテクノロジー。IoTなどの先進技術がもたらす“スマート農業”の基本をあらためて押さえるリアルとデジタルが重なり合う世界。「MR(複合現実)」が生み出す新たな体験
MR(複合現実)
2025年1月、世界最大級のテクノロジー見本市で話題を集めたのが、「MR(Mixed Reality)」を使ったメイクシミュレーションでした。「MR」とは「複合現実」を意味し、「VR」や「AR」と並ぶ没入型のデジタル技術の1つです。「VR」はゴーグルなどを着用して没入する仮想世界、「AR」は現実世界に文字や画像などを重ねて表示する拡張現実を指します。「MR」はいわばその両者を複合させた技術で、専用ディスプレイ越しに見る現実空間に仮想オブジェクトを配置し、環境と連動させながら操作・体験できます。例えば、冒頭のメイクシミュレーションは、ユーザーの顔の上に仮想メイクを施し、仕上がりをリアルに体験できるものです。最近では、ゲームやエンターテインメントにとどまらず、医療や製造業、建築業など幅広い分野で活用が進んでいます。さらなる発展が期待される「MR」の今後に注目しましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている MR(複合現実) に関連する記事はこちら
離れていても、同じ空間で寄り添う。VRがつなぐ幻肢痛の遠隔セラピー メタバースがもたらす消費行動の変化とは。新しい顧客体験によって生まれるビジネスチャンスを考える人類の知能をはるかに超えるAI。「ASI」の実現で世界は変わるか
ASI
AIの進化の究極系とされるのが、「ASI(Artificial Super Intelligence)」です。あらゆるタスクにおいて人間の知能をはるかに超える人工超知能を指し、以前紹介した「AGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)」がさらに進化したものといえます。「ASI」の能力は人間の1万倍にも及ぶといわれており、ビジネスにおいても、マーケティング戦略の立案や効果測定など、多くの分野で人間を凌駕する成果をもたらすとされています。「ASI」が実現すれば、シンギュラリティが起こり、社会は予測不可能な進歩を遂げるかもしれません。倫理的な懸念も大きく現在は研究段階にとどまっていますが、「AGI」が実現すれば、「ASI」の開発も加速することになると考えられます。果たして「ASI」の時代は訪れるのか。今後の行方に注目しましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている ASI に関連する記事はこちら
国際的AIコンペで1位を獲得。トップエンジニアが語る電通グループ×AIの未来(前編) AIでクリエーティブは無限に?「AI」×「人間のアイデア」で生み出す、これからのクリエーティブ(前編)小規模ビジネスの新たな潮流。ニッチ市場に特化した「Micro SaaS」の可能性
Micro SaaS
経理や総務などの事務作業をはじめ、今やビジネスに欠かせない存在となっているSaaS。その中でも、今回ご紹介する「Micro SaaS」は、名前の通りニッチな専門領域に特化したソフトウェアサービスを指します。例えば、オンラインカレンダーやWeb会議システムと連携し、空き時間を自動で共有・予約するサービスや、特定の業界に最適化した売り上げ管理ツールなどが挙げられます。「Micro SaaS」の市場が拡大している背景には、SaaSビジネスの成熟により大規模なSaaSではカバーしきれないニーズが生まれたこと、さらにAIの発達やノーコードツールの普及により技術的なハードルが下がり、スタートアップはもちろん、個人や小規模事業者などのスモールビジネスでも開発しやすくなったことがあります。現在は米国が先行している分野ですが、日本でも今後成長が期待されるビジネスモデルといえるでしょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている Micro SaaS に関連する記事はこちら
新興SaaSが実践する「PLG」とは何か?プロダクト主導のセールスモデルから新たな成長戦略を考える 新規事業や新サービスの成長を全方位的に支援する、「グロースコンサルティング」という新たなアプローチ(前編)