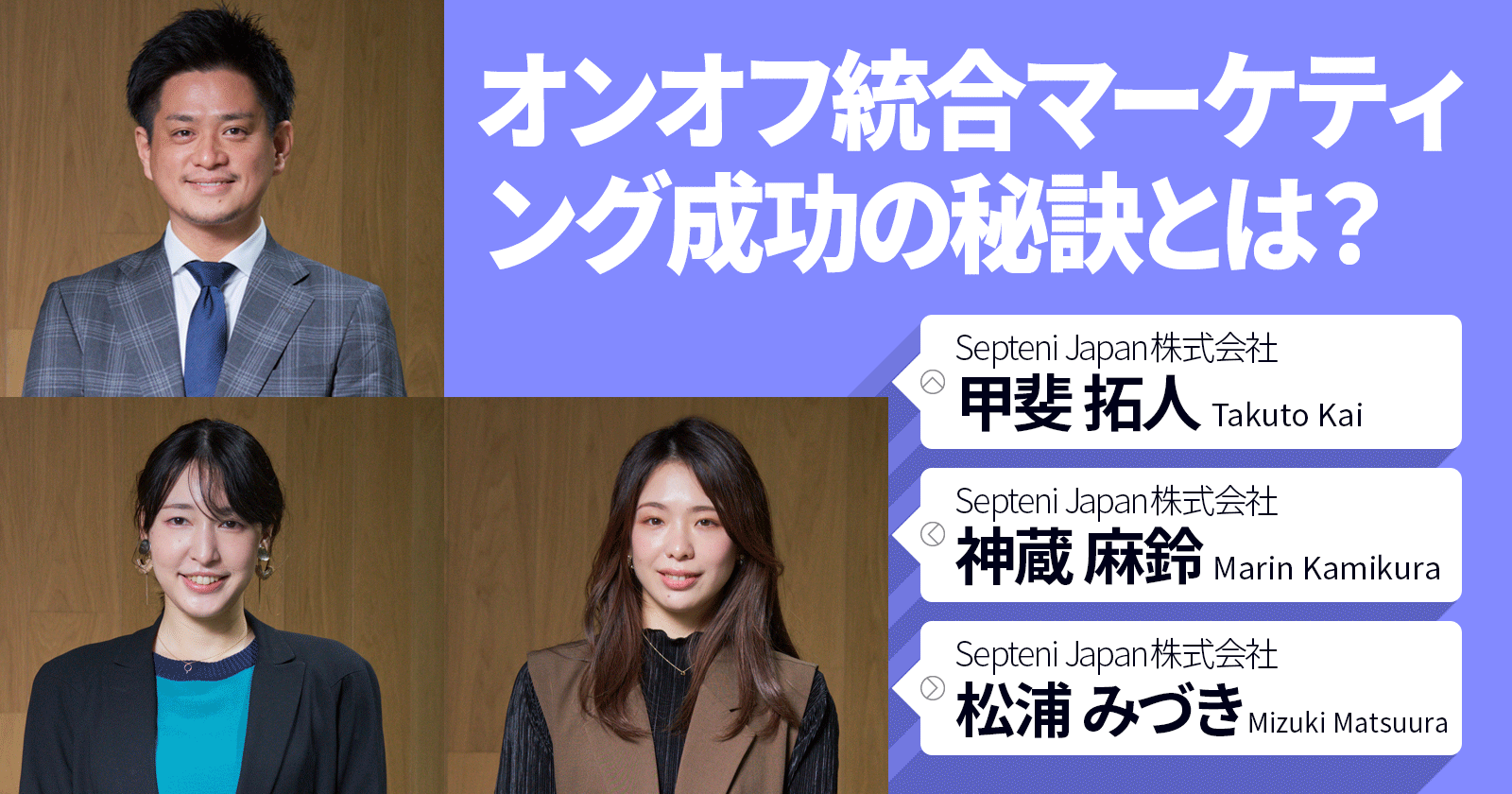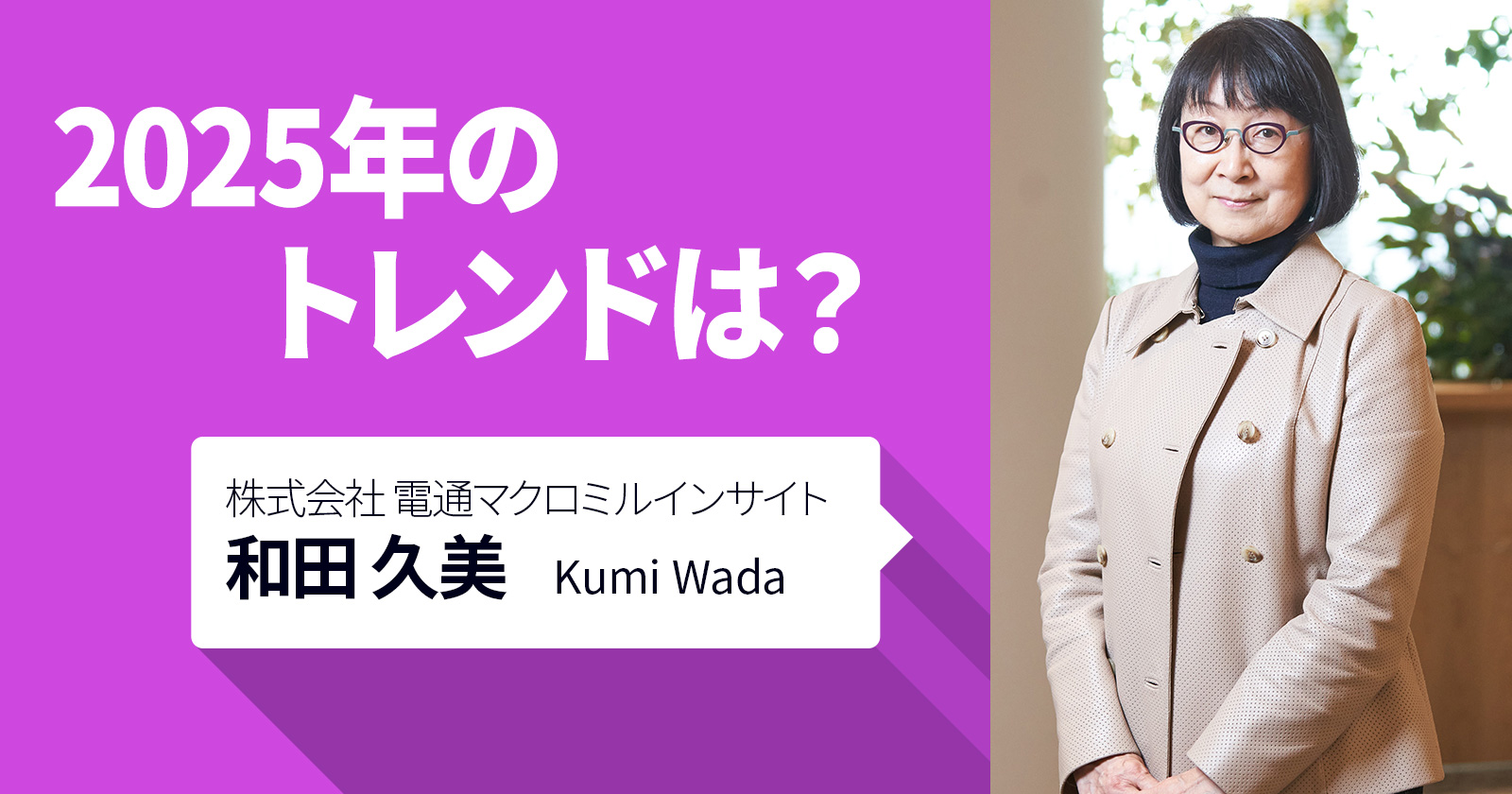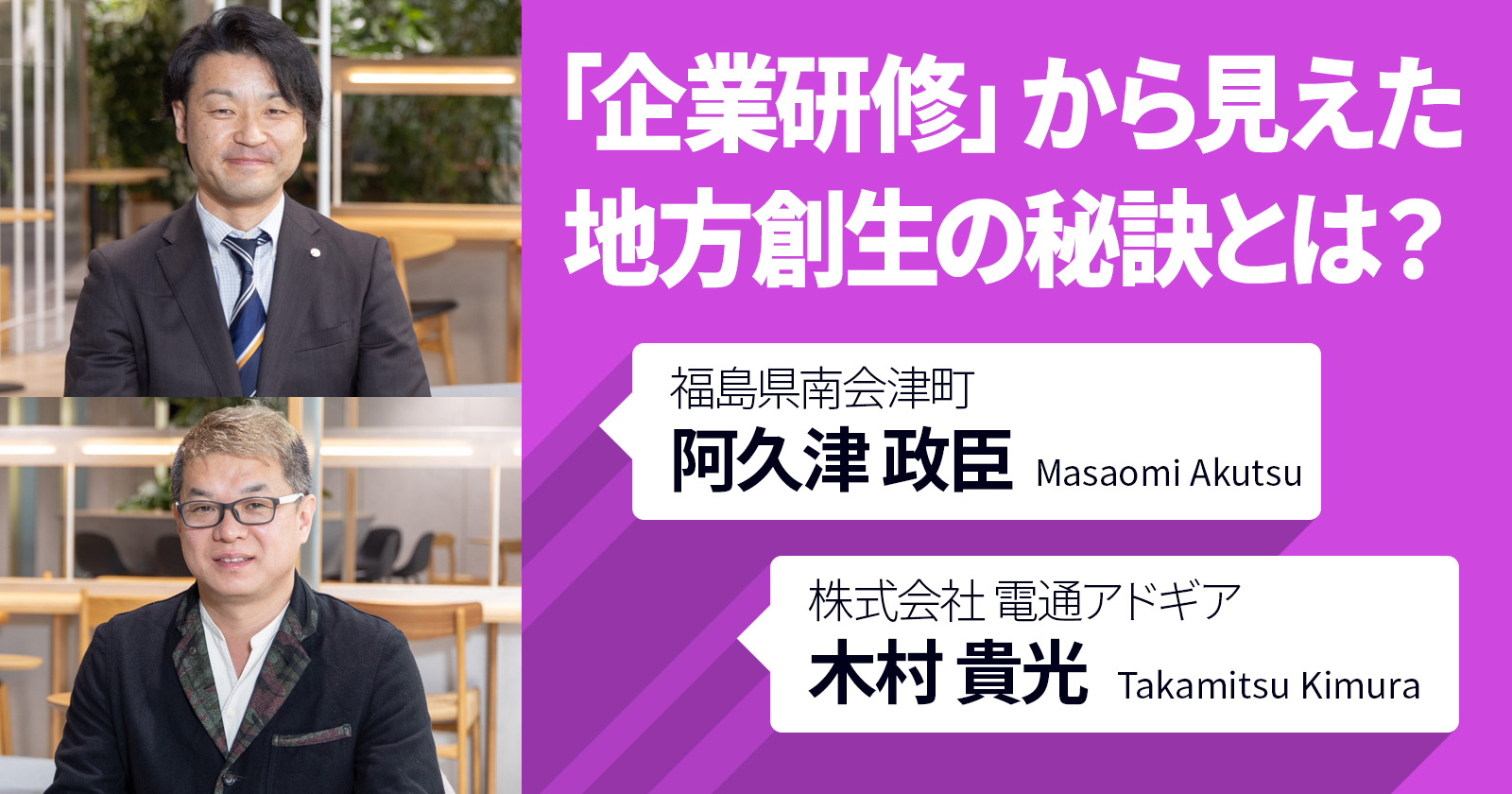インディペンデントの小さな紙メディア「ZINE」。令和の販促ツールに
ZINE
「ZINE(ジン)」とは、個人やグループが制作する小冊子を指します。コンビニ印刷やホチキス止めだけでも作れてしまう手軽さが魅力で、ルールや形式に縛られず、好きなものを自由に表現できるメディアとして注目を集めています。同人誌やフリーペーパーとも似ていますが、同人誌がマンガなどの二次創作が中心であるのに対して、「ZINE」は雑誌に近く、内容の自由度が高いこと、フリーペーパーのように無料とは限らないこと、などが違いとして挙げられます。手軽な表現という点ではSNSに近いメディアと言えますが、特定少数への発信という点が、不特定多数に向けた発信に疲れたSNS世代を中心に流行。さらに、紙媒体は、コロナ禍以降に需要が高まりつつあるリアルな集客との相性が良く、最近では、企業の販促やマーケティングへの活用も始まっています。SNSとは別のアプローチとして、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている ZINE に関連する記事はこちら
興味関心・ライフスタイルでSNSユーザーをグループ化。「Tribe Driven Marketing」に見るSNSデータ活用最前線(前編) “新刊” 「CXクリエイティブのつくり方」が目指したのはレシピ本?CXと料理の共通点とは出版不況の救世主に?地域活性化のカギともなる「ひとり出版社」
ひとり出版社
「ひとり出版社」とはその名の通り、1人またはごく少数で運営する出版社のこと。運営の小規模化によって、これまでの常識にとらわれないユニークなテーマで本づくりができることが強みの1つで、その数は年々増加。ヒット作も生まれています。かつては専門業者への依頼が必要だった印刷やデザインも自前で行えるなど、DX化によって参入のハードルが下がったことを背景とし、地方で創業するケースも見られます。そうした地方の「ひとり出版社」では、ローカルなテーマや著者を取り上げた作品が多く、地域活性化にもつながっています。ほかにも、シニア世代が支援サービスを利用し、本業の傍らで電子書籍専門の「ひとり出版社」を運営するケースもあり、「ひとり出版社」をめぐるビジネス形態は多様化しつつあります。出版不況が叫ばれる中、独自のアイデアで本づくりを革新する「ひとり出版社」は、大きなポテンシャルを秘めたトレンドといえるでしょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている ひとり出版社 に関連する記事はこちら
DXの時代、ハイスキル・フリーランス人材の活用が企業課題を解決に導く(前編) 金融の枠組みを超えて地域産業を振興。九州みらいCreationがつくる地域の未来(前編)書棚を借りて好きな本を共有。「シェア型書店」で新たな“推し活”現象も
シェア型書店
「シェア型書店」とは、1つの店舗内に複数の書棚を設置し、それぞれを異なるオーナーが運営する形態の書店のこと。シェア型にすることで運営のハードルが下がり、書店経営のノウハウを持たない個人でも気軽に参入できます。人気作品にとらわれることなく、「自分の好きな本を紹介したい」という趣味を起点に選書を行えるのも魅力で、人気の「シェア型書店」では空き棚のオーナーになるための抽選倍率が数十倍になることも。気に入った書棚のオーナーにファンが集まるのは、一種の“推し活”とも捉えられ、オーナーと客との交流も生まれるなどファンコミュニティービジネスとの親和性が高いといわれています。最近では、企業がこうしたスモールビジネスを支援するサービスも始めています。シェア型の運営が新たな価値を生みだす商品は、書籍以外にもあるかもしれません。探してみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている シェア型書店 に関連する記事はこちら
協調フィルタリングによる商品レコメンドのメリットとは。「ユーザーの好み」をベースにした商品との出会いはZ世代と好相性? コロナ禍でますます重要度が高まるECビジネス。ファンを増やし、成功させる秘訣とは?(前編)社会状況を科学的なエビデンスとして意思決定する政策形成手法「EBPM」
EBPM
「EBPM(Evidence-Based Policy Making)」とは、行政がエビデンスに基づいて政策の決定や実行、検証を行うこと。人口減少や財政不安など、国が前例のない課題に直面する中、限られた予算や人材を有効活用するために、統計情報に基づく比較検証や効果予測の重要性は高まっているといえます。デジタル技術の高度化でビッグデータの活用が可能となったことにより、実社会のリアルな動きや関心などをより正確に反映できるようになりました。また、「EBPM」の推進には市民とのコミュニケーションも不可欠。 例えば、英国が国民投票でEU離脱を決めた背景として、離脱による経済損失というエビデンスを国民に十分に伝えきれなかったため、民意が離脱に傾いたと指摘する声もあります。ITベンダーなどによる自治体向けの支援サービスも登場し、自治体DXを推進する上でもカギを握る「EBPM」。今後の動向を注視しましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている EBPM に関連する記事はこちら
ビッグデータを宝の持ち腐れにしないために。「DWH(Data Ware House)」活用の成功の秘訣とは?(前編) ESG経営の効果を可視化する。複雑な問題をAIで読み解く試みとは(前編)新興国の目覚ましいリープフロッグ型進化。インドの電子決済システム「UPI」とは
UPI
日本でも普及しつつあるキャッシュレス決済ですが、アプリ間の互換性に乏しいなど、今なお課題は残ります。その解決策として日本政府も注目しているのが、「UPI」と呼ばれるインドの決済システム。スマートフォンを利用した銀行間の相互送金システムで、「UPI」に対応していれば、利用者は自分や相手が使用しているアプリの種類に関わらず、手数料なしで即時決済が可能。決済にはQRコードを利用でき、相手に口座番号を伝える必要もありません。高額紙幣の廃止やコロナ禍で現金使用を避ける傾向が強まったことも追い風となり、インドではクレジットカードよりも高い利用率を誇ります。新興国で新しい技術やサービスが一気に普及する「リープフロッグ型」の進化であり、強いイニシアチブを持つ決済公社が存在するインドだからこその施策ともいえますが、ここから得られるヒントは多いでしょう。日本政府の動向を含め、今後の展開を追っていきましょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている UPI に関連する記事はこちら
BNPLはZ世代になぜ人気?後払いの新しい決済スタイルとは。魅力的なCXのヒントにも 増加し続ける「コンタクトレスエコノミー」とは何か?CX設計の重要性と共に考える