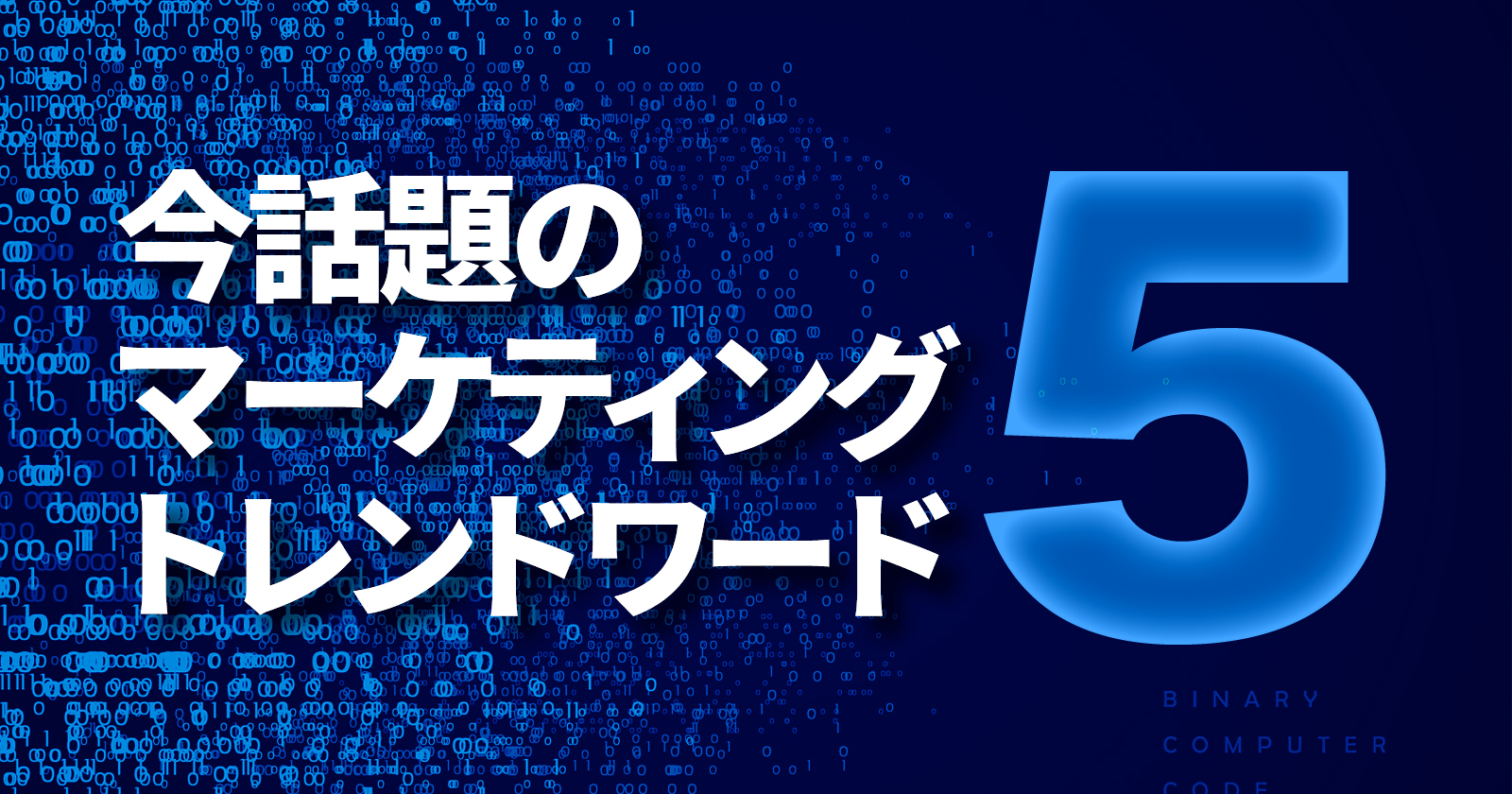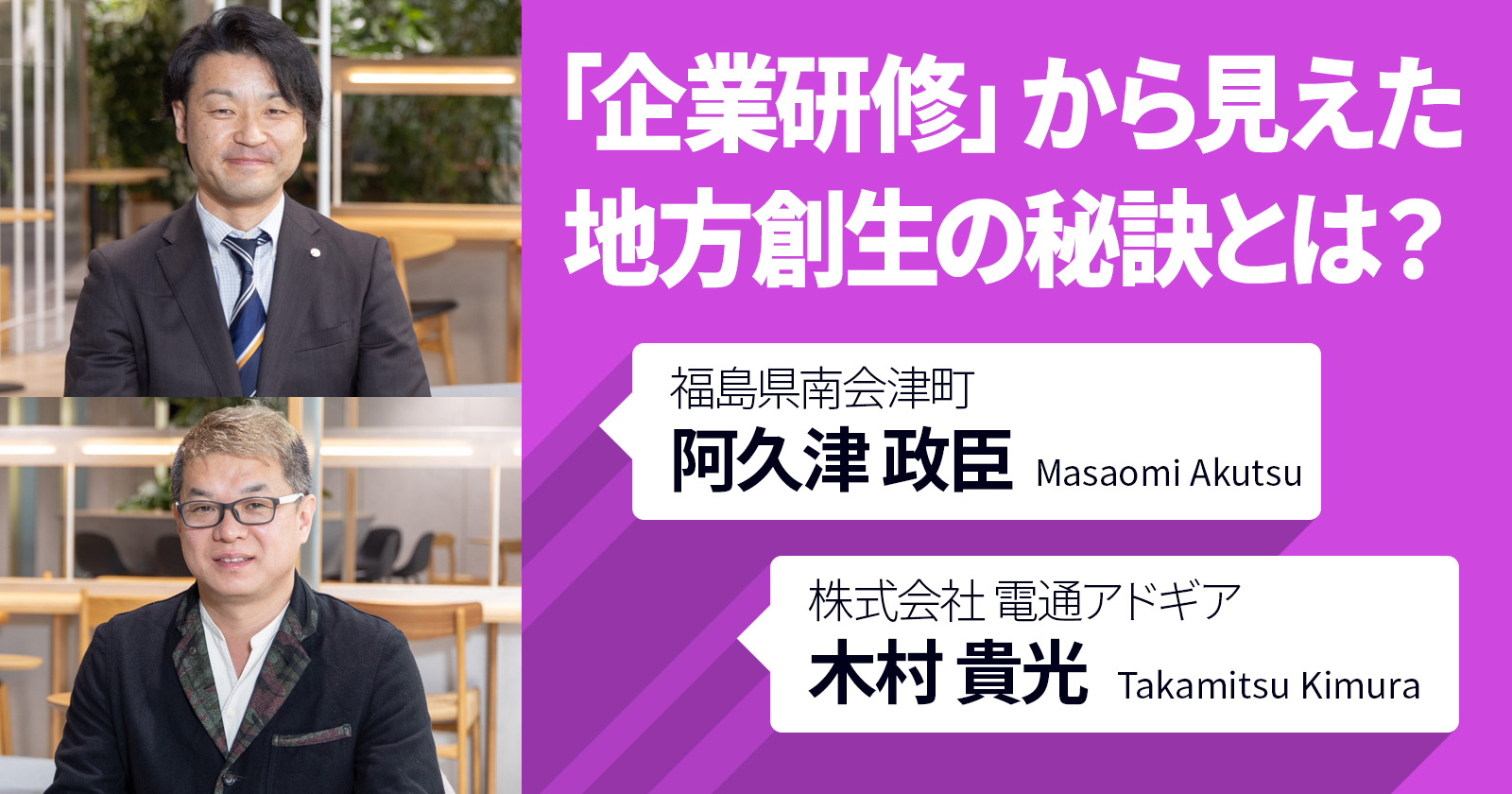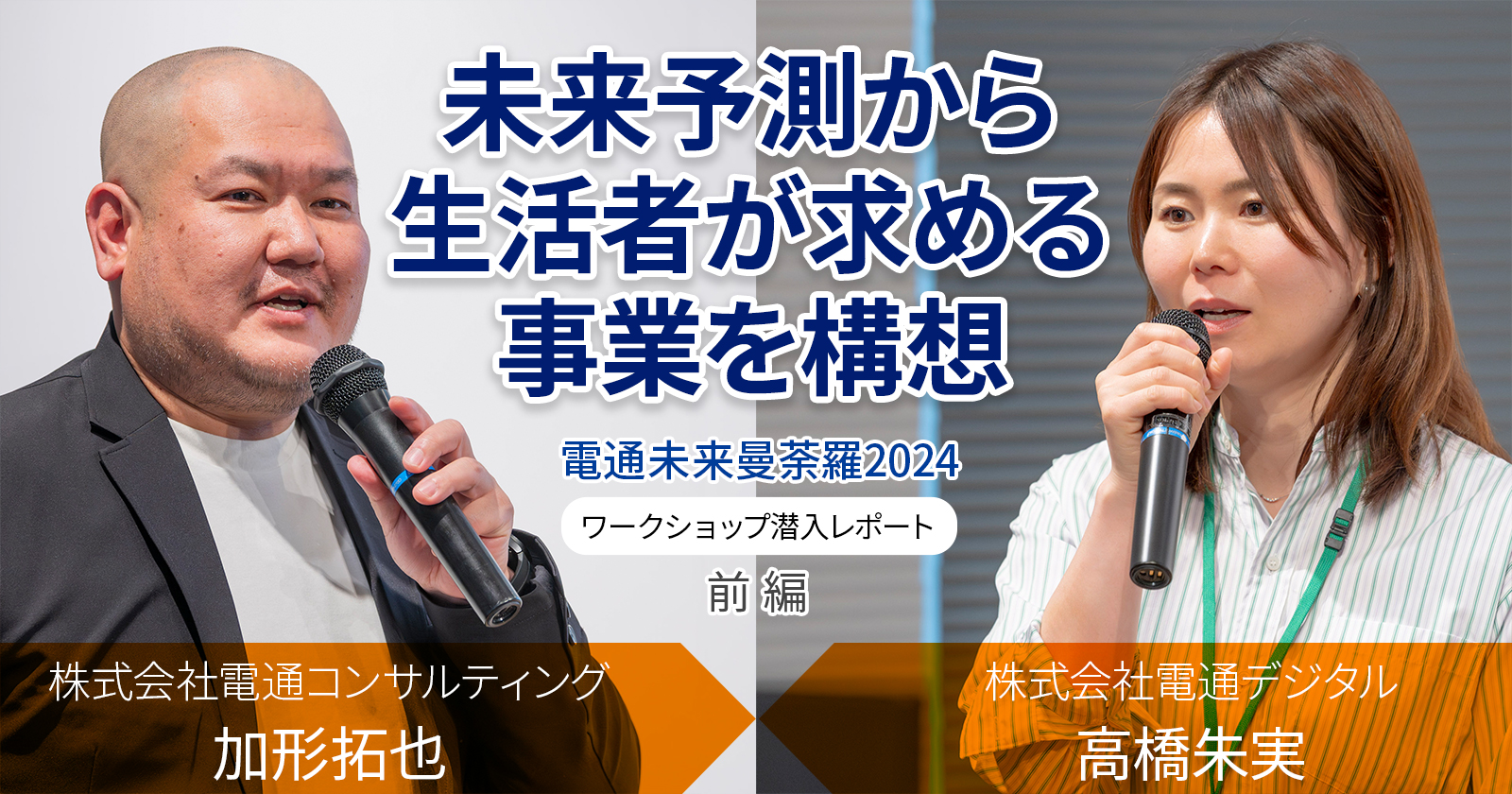ドライバーと企業の共創関係を生み出す「マイカー広告」
マイカー広告
「マイカー広告」は、個人所有の自動車(マイカー)に企業のステッカーを貼る新たな広告手法です。ドライバーは走行距離に応じて広告収入を得ることができ、企業は比較的低コストで幅広い層にリーチできる点が特徴です。代表的なサービスでは、申し込みからステッカーの受け取り、走行距離に応じた報酬ポイントの獲得までをスマートフォンで完結させることが可能。副業の普及なども追い風となり、日本でも徐々に活用が進んでいます。特定の地域を走る車に広告を出すこともできるため、ローカルビジネスやキャンペーン型広告との相性が良く、自治体が活用するケースも見られます。一般ドライバーの運転品質への懸念はありますが、厳格な規約を設けることなどの対策をとっている企業も。また、広告車両であることによる安全運転の意識向上も期待されています。「マイカー広告」の市場は成長途上にあるため、早期参入で大きな効果を狙ってみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている マイカー広告 に関連する記事はこちら
DIで進化するB2Cグロース戦略を、コロナ禍の「鉄道業界」を例に考える(前編) マス広告のハードルを下げ、課題解決の間口を広げる。「ウリアゲガンバ」をコミュニケーション活動のファーストステップに推し活が生活の中心に。自治体も期待する「聖地移住」
聖地移住
アニメや映画、ドラマなどの舞台を訪れる「聖地巡礼」はすっかり定着しましたが、さらに進んだ現象として注目されているのが、ファンが作品の舞台に生活圏を移す「聖地移住」です。推し活の盛り上がりやリモートワークの普及を背景に、20~30代を中心に「聖地移住」を行う人が増えています。こうした動きを受けて、自治体がファン向けの移住相談会を開いたり、「聖地移住」に関する論文が発表されたりなど、行政や研究機関の関心も高まってきました。大ヒットアニメの舞台となった静岡県沼津市や茨城県大洗町など、聖地移住者が100人を超える自治体も存在します。移住者と地域住民との関係構築といった課題はあるものの、「聖地移住」は観光から定住への移行を促し、税収増やファンマーケティングによる経済効果が期待されます。地域活性化に貢献する推し活の進化形として、その可能性に注目してみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている 聖地移住 に関連する記事はこちら
自然栽培ではなく、意思を持ってファンを育む。「Fan Farming CX」で築くファンとの幸せな関係(前編) 超専門メディア運営に学ぶ、「ファンマーケティング」実践術自動運転やスマート農業に欠かせない存在に。GPSより高精度な「GNSS」
GNSS
「GNSS(Global Navigation Satellite System)」は、「全地球測位衛星システム」を意味し、地球上のどこにいても正確な位置情報を取得できる衛星測位システムの総称です。なじみのある「GPS」は米国が単独で運営するシステムですが、「GNSS」は世界各国が運営する衛星システムを活用するため、GPSより高精度な測位が可能。例えば「GNSS」は、自動音声による観光ガイドなどにおいて、GPSでは捉えられない利用者の体の向きまで把握することによって、より適切な案内を実現してくれます。また、その精度の高さを生かし、観光業界だけでなく、自動運転やスマート農業、ドローンなど幅広い分野で活用されています。私たちが「GPS」と呼ぶシステムが、実は「GNSS」であることも少なくありません。IoTの重要性が高まる中、今後のビジネス発展に欠かせない技術といえるでしょう。
Transformation SHOWCASEで扱っている GNSS に関連する記事はこちら
農業ビジネスを変革するテクノロジー。IoTなどの先進技術がもたらす“スマート農業”の基本をあらためて押さえる IoTを"Internet of LIFE"へ。生活密着型ビジネスづくり”3つの法則VUCA時代に求められる柔軟な思考法「エフェクチュエーション」とは
エフェクチュエーション
「エフェクチュエーション」とは、米国のビジネススクールの教授が提唱する、成功した起業家に共通して見られる意思決定プロセスです。未来を予測し、目標を設定してから手段を検討する「コーゼーション」とは異なり、手元のリソースを活用しながら柔軟にゴールを設定していくアプローチで、不確実性の高いVUCA時代に対応するための実践的なフレームワークといえます。「エフェクチュエーション」には5つの原則があり、例えば「レモネードの原則」は、予想外のアクシデントを新たなチャンスに変える考え方で、失敗作が思わぬヒット商品になるケースなどがその成功例として挙げられます。2024年には「エフェクチュエーション」に関する書籍がヒットし、「日本マーケティング本 大賞2024」を受賞するなど関心が高まっています。新規ビジネス開発にも役立つため、新年を迎えた今、学びを深めてみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている エフェクチュエーション に関連する記事はこちら
壊れたモノに、テクノロジーの力で付加価値を。Dentsu Lab Tokyoが「アップサイクルの可能性展UP-CYCLING POSSIBILITY」を開催 人の意思決定や行動をデザインする「ナッジ」とは?行動経済学を取り入れたマーケティング施策を考える音を使ってブランド価値を高める?「ソニックブランディング」のすすめ
ソニックブランディング
「ソニックブランディング」は、音を使ってブランドの認知度アップや記憶への定着を図るマーケティング手法のことです。「オーディオブランディング」とも呼ばれ、視覚的なロゴやスローガンと同様に、特定の音やメロディーがブランドを象徴することで、消費者はその音を聞いただけで商品やサービスを瞬時に思い浮かべるようになります。具体的には、広告に使われる楽曲やサウンドロゴのほか、電子マネーの決済音やサブスクの起動音なども「ソニックブランディング」に含まれます。音は目から入る情報に比べて伝達速度が速く、正確に伝わりやすいとされ、ユーザーの好感や共感を引き出しやすい点が強みです。近年、Podcastや音声広告などの音声メディアが普及し、メディア環境が変化する中で、「ソニックブランディング」はこれまで以上に注目されているといえるでしょう。自社のブランド戦略の一環として取り入れてみてはいかがでしょうか。
Transformation SHOWCASEで扱っている ソニックブランディング に関連する記事はこちら
Web3.0でリスナーに新たな体験をもたらす「J-WAVE LISTEN+」の成功の秘訣とは?(前編) Z世代が倍速視聴を好む理由とは?これからのコンテンツ戦略で意識するべき、傾向を探る